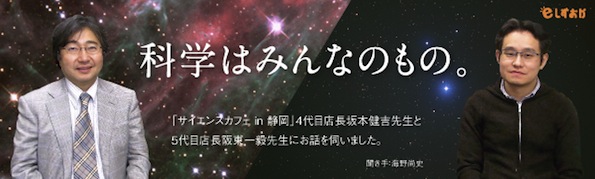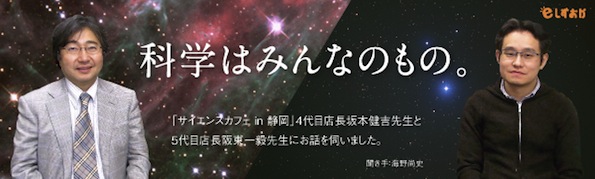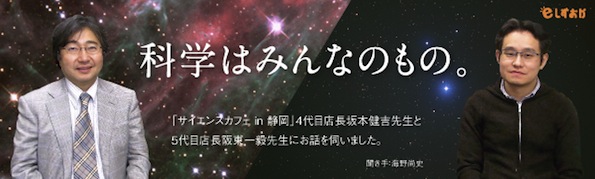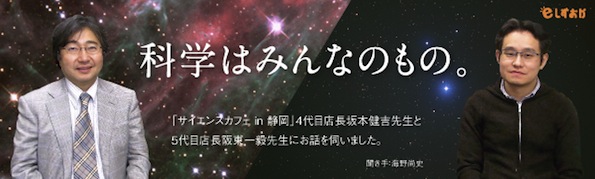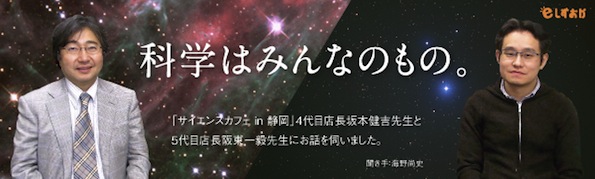 東日本大震災が起きてその約1ヶ月後、
東日本大震災が起きてその約1ヶ月後、
「地震と放射能:いま知っておくべきこと」と題した緊急セミナーが
静岡市で開催されました。地震について様々な情報が錯綜する中で
静岡市民にむけて本セミナーを企画した「サイエンスカフェ in 静岡」。
会場で聞かれた「地震のことがよく理解できた」「安心しました」
という市民の声は、インターネット社会になり多くの情報があるにもかかわらず、
私たちの暮らしの中には自分では取り除くことのできない不安があることの
現れだったように思えます。
放射能、地球温暖化、遺伝子組み換え食品、環境ホルモンに狂牛病etc…、
科学が発達して便利な世の中になるにつれて、
わたしたちの暮らしを取り囲むさまざまな科学的問題。
生活を豊かにしてくれた多くの工業製品や自然に対する素朴な疑問と、
「わたしたちの周りで、今何が起きているのだろう」という漠然とした不安は、
科学に触れることで軽減できるのもしれません。
東日本大震災後の緊急セミナーから約1年が経った今、
同セミナーを企画した静岡大学理学部の先生であり
「サイエンスカフェ in 静岡」の4代目店長坂本健吉先生と
5代目店長の阪東一毅先生にお話を伺いました。
・「サイエンスカフェ in 静岡」とは
静岡大学理学部で最先端の研究をしている先生を講師に迎え、 科学の話を地域の人が気軽に聞けるカフェスタイルの場。 過去6年間で、延べ5000人以上の市民が参加。地球温暖化、クローン生物、環境ホルモン、新機能性物質の合成など、社会的に大きな関心を集めている分野から、「ブラックホール活動天体への招待」「アルキメデスの失われた写本を読む」「富士山で見られる南極と北極の世界」「遅い光と速い光」など、科学のロマンを感じさせるお話まで、幅広いテーマをとりあげている。開催場所は、B-nest静岡市産学交流センター。
▶ 坂本健吉さん:静岡大学 理学部科学課 教授 (写真左)
阪東一毅さん:静岡大学 理学部物理学科 講師(同右)
▶「サイエンスカフェin 静岡(ブログ支店)」:
http://sciencecafe.eshizuoka.jp/
▶「サイエンスカフェin 静岡」公式サイト:
http://www.sci.shizuoka.ac.jp/sciencecafe/
▶ 静岡大学理学部公式サイト:
http://www.sci.shizuoka.ac.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◀【1】から読む
【4】地震と放射能の話は、静岡での生活と切り離せない
海野 便利な世の中になってきましたが、
市民ではなかなか判断のつかない問題も増えています。
生活の中での科学の知識は重要です。
市民も専門的な知識があればいいのでしょうが、なかなかそうもいかない。
判断がつかない時に市民はどうすればいいのでしょうか?
坂本 自然科学だけでなくどんな分野であれ、
論理性がなかったら研究はできません。
どんな論理で研究しているのか聞いていただければ…と思います。
海野 論理ですか…。
坂本 今の科学でもわからないことは山ほどあります。
でも、科学でわかっていることもたくさんある。
「そんなことはありえない」ということもあるんです。
海野 たしかにそうかもしれない。
坂本 科学の論理に触れていただければ
「そんなことはありえないだろう」「それは正しいんじゃないか」
ということが、ある程度は感覚的にわかるようになるんじゃないでしょうか。
海野 東日本大震災の1ヶ月後に開催した地震と放射能の話は、
静岡市民の不安を軽減する大きな役割を果たせたように思います。
坂本 浜岡原発がありますし、東海地震が取りざたされている静岡では、
地震と放射能の話は、生活と切り離せない重要なテーマです。
東日本大震災が起きて1ヶ月ほど経った頃、とにかく大騒ぎしていた時期に、
放射科学研究施設の奥野先生と大谷先生の二人に話していただきました。
おふたりは、放射能の基本的な、教科書的な話をしてくれました。
海野 教科書的なお話?
坂本 「放射線とは何か」「放射能とは何か…」というようなお話ですね。
福島の話にはほとんど触れず、原子炉の話もしなかったことが、
かえって評判がよかった。
海野 といいますと?
坂本 いま福島がどうなっているか、などはもちろん誰もが気になりますが、
それ以前に、放射能や放射線の基礎知識を共有しておくことが大切だろうと。
放射線にはα線、β線、γ線があって…というところから確認したことで、
参加者からは「とてもよく理解できた」「安心した」という声をいただきました。
海野 たしかにニュースは、そこまで掘り下げて説明してくれない。
坂本 テレビでは「何十万ベクレル」とか「シーベルト」などの
数字ばかりがクローズアップされがち。
それらは原子の話なので数字が大きくなるのはあたりまえ。
むしろ驚くべきは、数十ベクレルという小さな数値が計測できていることです。
原子1個レベルの測定が出来ていること事体がすごい。
海野 なるほど、驚く視点が違いますね。
坂本 地震については、実際に地震発生のメカニズムを研究していた
生田先生に話していただいた。生田さんは
「自分は今回の地震をまったく想定していなくて、
地震学者として恥ずかしい。
だから、とても怖いけど、その思いも込めて話したい」
とおっしゃって引き受けてくれたんです。
海野 勇気がありますね。
坂本 あのとき、生田さんは「全容はまだわからない」というところから始めて、
とても誠実なお話をした。
質疑応答では、静岡で予想される駿河湾における津波についての質問もありました。
かなり早い段階で、そのような話ができたことはよかったと思います。
海野 静岡県民にとって切実な話を、地元静岡大学の先生から
直接聞けたことも本当によかった。
坂本 あれから1年経ちます。
それから最近では富士山の噴火の話もありますので、
近いうちに、もう1回開催してみたいですね。
海野 ぜひお願いします。これから静岡の市民に伝えたいことはありますか。
阪東 繰り返しになりすが、若い方に来ていただきたい。
理学部では中高生向けに大学で研究を体験できる
「未来の科学者講座」プロジェクトも開催しています。
「未来の科学者講座」に参加してくれた中高生も
サイエンスカフェに参加してくれていて、
すこしずつ広がりを実感しています。
坂本 わたしは、お母さんたちにも来ていただきたいですね。
会場の確保などが難しいのですが、できれば託児所を用意したいほど。
放射能の話でも、マスコミの情報で一番怖がっているのはお母さんたちです。
お母さんたちの不安を取り除いてあげたり、
ご自分で判断できるようになるためのお役に立ちたい。
海野 中高生やお母さんたちで賑わう会場を早く見てみたいですね。
今日は、ありがとうございました。
坂本 ありがとうございました。
阪東 ありがとうございました。
海野 これからも「サイエンスカフェin 静岡」を楽しみにしています。
・ ・ ・
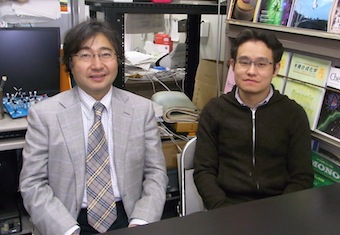
【1】そもそも何の目的でスタートした?
【2】 自然科学的なものの見方が助けになる
【3】「宇宙」「富士山」「化石」が人気
【4】地震と放射能の話は、静岡での生活と切り離せない