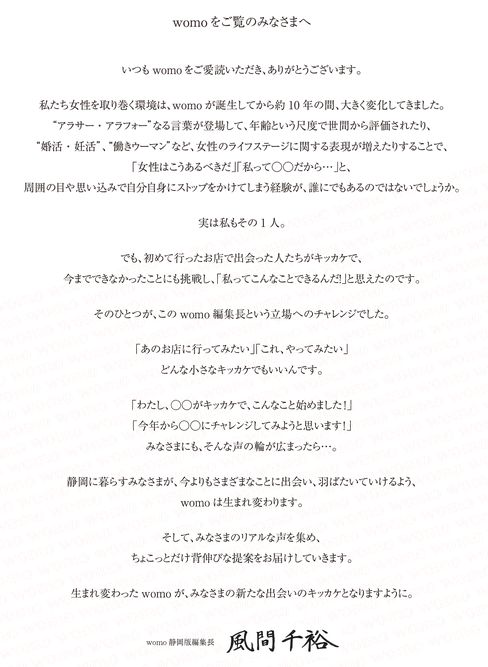フリーマガジン『womo』リニューアル号が発行となりました。
2015年に『womo』は10周年を迎えます。この10年は、日本も、静岡や浜松の街も、そしてわたしたちを取り巻く環境にも、大きな変化がありました。そんな変化を受け入れつつ、わたしたちの街での生活を、今まで以上に充実したものにしたい、と誰もが願っているのではないでしょうか。
それら時代の変化にあわせ、みなさまの声に今まで以上に応えられるように『womo』をリニューアルすることにしました。編集長も新しく風間千裕さんにバトンタッチ。11月号は、新編集長の風間千裕さんを中心に、この夏、社内に立ち上げた「womoハッピープロジェクト」のメンバーが準備してきた充実の誌面となっています。
「womoハッピープロジェクト」のメンバーのほとんどは、読者のみなさまと同世代のスタッフです。自らも読者のみなさまと同じ街にも暮らす、いち読者として、楽しみながら新しい『womo』を作り上げました。ぜひ、手に取ってお楽しみください。
新しい『womo』をみなさまにお届けできることの高揚感と、わたしたちの思いが読者のみなさまにしっかりと届くだろうかという不安が入り交じった気持ちでいっぱいですが、11月号だけでなく、これからもスタッフ一同、みなさまにたくさんの笑顔をお届けできる『womo』を創っていきますので、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
『womo』誌面でも掲載していますが、風間新編集長から読者の皆まさへのメッセージがあります。ぜひ読んでいただけるとうれしいです。
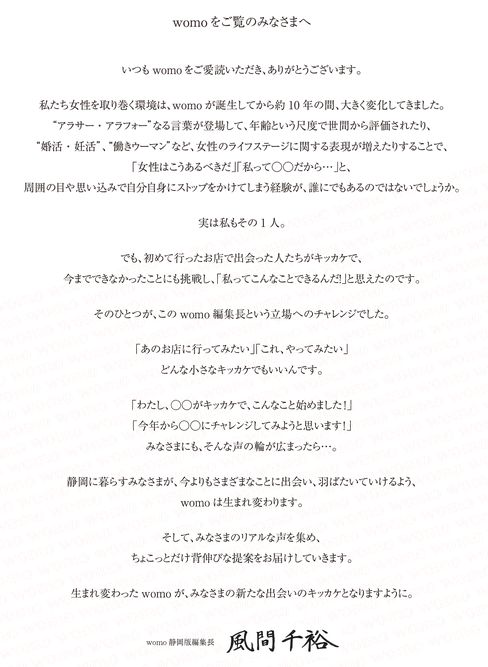

静岡のママ作家さんのハンドメイド作品をスマホで購入できる新しいサイト『
mamaneマルシェ』(スマホ専用)がオープンしました。
出品されている作品は、ママ作家さんがひとつひとつが手作りした作品ばかり。とてもオシャレで素敵な作品が揃っています。気に入った作品は、スマホでその場で購入(直接自宅に届きます)することができるサービスです。
スタート時点の作品数は103点からですが、みなさまのお気に入りの一品がみつかるように、ママ作家さんも作品もさらに増やしていきます。
お子さまや、お友だち、姪っ子・甥っ子に、お孫さんにプレゼントを贈りたいと思ったときは、『
mamane(ママネ)マルシェ』を、ぜひチェックしてみてください。
『
mamane(ママネ)マルシェ』は、「静岡のママをもっとかわいくハッピーに」「ママと社会とのつながりを応援する場をつくる」というmamane(ママネ)のコンセプトをもとに、弊社ママスタッフが考えたサービスです。
▼mamane(ママネ)マルシェ ※スマホ専用です
http://womo.jp/mama/marche
オープニングイベントとして、12月12日(金)、13日(土)に、マークイズ静岡で『mamaneマルシェ@マークイス静岡』を開催します。
▼mamane(ママネ)マルシェ@マークイズ静岡 ※スマホ専用
http://womo.jp/mama/marche/lookup/event01.html
当日は、mamaneマルシェに参加している作家さんが出店するほか、撮影会やリトミック、積み木遊びなど、親子で楽しめるイベントも予定しています。



静岡県立美術館で開催中の「
美少女の美術史」会場に展示された日本の美少女(写真上)と、東京国立近代美術館フィルムセンター展示室で開催中の
「ジャック・ドゥミ 映画/音楽の魅惑」展の美少女たち。
昨年パリのシネマテーク・フランセーズで開催されたジャック・ドゥミ展が、東京国立美術館フィルムセンターで開催されている。それほど期待しないでぶらりと寄ってみたのですが、これがとてもよかった。
「美少女の美術史」で表現されているような日本的なイメージの「カワイイ」世界とは別に、ミュージカル映画『
ロシュフォールの恋人たち』(1967年)などの、おしゃれな服装、カラフルな色彩、ミシェル・ルグランの軽快な音楽とダンス、思春期から大人への境界の特権的な瞬間を描いたドゥミの世界にはフランス的な「カワイイ」を感じる。
ジャック・ドゥミの映画『
シェルブールの雨傘』(写真下)でヒロインを演じたフランスの美少女カトリーヌ・ドヌーブ。米澤よう子さんの描く「womo」の表紙に登場するトレンチコートを着た女性を見ると、いつも『シェルブールの雨傘』のカトリーヌ・ドヌーブを連想してしまうのだが、これは偶然なのかな。
 『mamane(ママネ)マルシェ』10/21(火)にOPEN!
『mamane(ママネ)マルシェ』10/21(火)にOPEN!


渋谷・道玄坂上の雑居ビルの3階にオープンした「
森の図書館」。いまから25年も前のことではあるが、道玄坂裏の神泉駅近くにあった仕事場に2年ほど通っていたことがあり、このあたりは懐かしい。
「森の図書館」は、「キャンプファイアー」というクラウドファンディングサイトで、1,736名という日本記録の支援者を集めた(集めた資金総額は約950万円)企画として知られる。短期間にそれほど多くの人が支援者として手を挙げたのは、「みんなが自由に本が借りられて、お酒が飲める場所があったら絶対便利で楽しいと思う」 という、「森の図書館」の発案者で本好きの森俊介氏の夢に共感した人がいかに多かったか、ということでもある。
「森の図書館」のコンセプトは「
本が読めて、借りられる。お酒が飲める。音楽が楽しめる。むかし遊びにいった、友だちの家のように気軽な空間」。入店するためには、入り口のインターフォンで声をかけなければならない。この作法は、たしかに、誰かの家を訪ねるときの手続きである。
書棚の蔵書を借りることができる点では「図書館」であり、店内の雰囲気やメニューは洒落たブック・カフェ&バーのよう。蔵書は、比較的よく読まれている売れ筋のものが多い印象。特定のタイプの客層に絞ることなく、幅広く誰にでも気軽に利用してもらうためのラインナップなのだろう。自宅でも職場でもスタバでもない、「第4の場所」の今後の広がりが楽しみ。
『mamane(ママネ)マルシェ』10/21(火)にOPEN!


いつまでも大切に何度も読み返したい本のひとつに、須賀敦子の作品がある。須賀敦子が生前に出版した本は、わずか5冊(『ミラノ・霧の風景』『コルシア書店の仲間たち』『ヴェネツィアの宿』『トリエステの坂道』『ユルスナールの靴』)。彼女の新しい作品はもう読めないのだと諦めていたが、文藝別冊『
須賀敦子ふたたび』に、全集に収録されなかったエッセイ3編(「コスモスの海」「ナタリアの家族」「私の好きな映画」)が掲載されている。これはしあわせなこと。
そのほか、松山巌氏による評論「多面体としての須賀敦子」、対談「松家仁之×湯川豊」、座談会「編集者からみた須賀敦子の素顔」など。彼女の映像的で華やかな文章、エッセイと小説の世界が行ったり来たりするような表現はどのようにして生まれたのかなど、須賀敦子の作品の背景を垣間見るようで興味深い。
以前、彼女の短いエッセイ『となり町の山車のように』のこと(「
摘まれないキノコ」)を書いた日も雨だったが、今日も外は荒れ模様。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇◇『mamaneシアター』10月 開催概要◇◇

■開催日時:2014年10月30日(木) 10:00~
■参加条件:子どもをもつママ(0歳、1歳ママが対象)
■開催場所:シネシティ ザート(新静岡セノバ9F)
詳しくはこちら ↓ ↓
http://womo.jp/mama/theatre/index/tpl/index/

10月18日(土)~24日(金)の映画『
子宮に沈める』の
静岡シネ・ギャラリーでの公開に先駆けて、本作品に主演した静岡市出身の俳優・伊澤恵美子さんに
インタビューさせていただいた。
映画『
子宮に沈める』は、実際に大阪で起きた育児放棄(ネグレクト)の事件をもとにした作品。「いい母親」というイメージや「母性」という言葉の重圧、そこに経済的な困窮などが加わって、社会から孤立し追いつめられていく母親の姿に、報道からは知り得ない一面が描かれている。
「
事件を起こしてしまったお母さんは、最初は自分からは遠い存在でしたが、調べれば調べるほど、何かのきっかけで、自分にも虐待をしてしまう可能性がどこかにあるかもしれない、と思うようになっていきました。演じる役が自分ごとに感じられるまで、突き詰めていきました」(伊澤恵美子さん)
お子さんどころか、結婚もしていない伊澤さんも、世の中のお母さんがおかれている状況や、抱えている孤独感を知ることで「自分ごと」として受け止められるようになったそうです。映画ではシングルマザーを取り上げていますが、ふつうのお母さん、そしてふつうの社会人に劇場に足を運んでいただくことで、自分たちのまわりで起きていることへ関心をもつきっかけになるのではないかと思います。
インタビューの後は、七間町に新しくオープンした
スノドカフェ七間町で開催された映画上映連動企画「伊澤恵美子トークライブ&朗読会」にもでかけてきた。演劇からキャリアをスタートした伊澤さんらしく、『子宮に沈める』の母親役とは真逆の、活き活きと力強いライブ(朗読)でした。伊澤さんは、2015年夏公開予定の日本・タイ合作映画『
アリエル王子の監視人』にも主演。これからの活躍が楽しみです。
伊澤恵美子さんのインタビューは、【
日刊いーしず】「
インタビューノート」にアップします。
追伸:イベント会場の
スノドカフェ七間町では、マフィンがおすすめ!
・映画『子宮に沈める』公式サイト
http://sunkintothewomb.paranoidkitchen.com/
・静岡シネ・ギャラリー
http://sarnathhall.eshizuoka.jp/
・【日刊いーしず】インタビューノート
http://interview.eshizuoka.jp/e1374881.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★「ランチパスポート静岡・西部」好評発売中!★
これ1冊で掲載されている700円以上のセットメニューが全て500円になる
超おトクなランチ本!ご購入は、お近くの書店、またはコンビニまで♪
▼ランチパスポート静岡
http://f.msgs.jp/r/c.do?i7C_1HQ_BW_xvu
▼ランチパスポート西部
http://f.msgs.jp/r/c.do?i7D_1HQ_BW_xvu

今から約10年前、静岡市の静岡県男女共同参画センター「あざれあ」で開かれた「東海電子自治体戦略会議2005」の基調講演で登壇したのが、TRONプロジェクトのリーダーで東京大学教授・坂村健氏だった。テーマは、「
人間社会を高度に支援するユビキタスコンピューティング」。
この時の坂村健先生のお話で、いまでも強く印象に残っているのが「
技術はこれからも進歩するが、そこで得た技術でどんな社会を作ろうとするのか。それを判断する時に重要なのが教養である。3年先、5年先のことを決める時に、教養など役に立たないと思うかもしれないが、30年先、50年先のことを決めるとき、そして、その新しい技術が社会にどんな影響を与えるのか予測がつかない時の判断に、教養は不可欠である」(うろ覚えだが、こんな主旨だったと思う)というお話。それから、理系偏重の社会や大学教育のことも心配されていた。
それから10年。坂村先生の声がようやく世の中に届いたのか、今年に入って教養(リベラルアーツ)が見直されているようである。最近でも『
Think!東洋経済』が「なぜ世界のエリート達は、リベラルアーツを学ぶのか?」という特集を、『
日経ビジネスアソシエ10月号』では、ズバリ「仕事と人生に差がつく教養入門」という特集を組んでいる。
背景にどんな変化がおきているのかはわたしの知るところではないけど、企業においては、「
事業環境の変化が早く、予測も難しい中で、ブレない意思決定をするためには、自分なりの価値体系が大きな助けとなる」ということだろう。また、「
多様な人材・文化を理解し、社内に受け入れ、そこから新たな価値を創造していく上でも、教養がものをいう」ということももっともである。
実際、わたしたちのような中小企業においては、30年先、50年先どころか、1年、2年先の予測さえ難しい。ましてや新規事業など、利益計画は作るものの、ささやかな外部環境の変化で計画そのものが簡単に吹き飛んでしまう。
そのような日々の業務の中で、過去の成功体験を捨て、やり方を変え、新しいことに踏み出すには、社内の合意をとることに大きなエネルギーを要する。そして、合意形成がうまくいくかどうかは、関係者がどんな価値観の持ち主であり、思考性を持っているか、が重要なのだと思うが、それがまた難しいのが中小企業の苦しいところなのではないだろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『womo』夜カフェ特集:ドリンク・料理・デザート1500円!
要予約のお店、曜日限定のお店が多いのでお出かけ前にチェックしてください。
詳しくはこちら↓


第4回「
mamane(ママネ)シアター」を開催しました。会場は、シネシティザート(新静岡セノバ9F)。「
mamaneシアター」は、ママネが運営する、家事に育児に奮闘する毎日を送っているママのための映画会。今回は17名のママさんが参加してくれました。お忙しい中、ありがとうございました。今回選んだ作品『
猿の惑星:新世紀 ライジング』は、楽しんでいただけましたか。
4回開催してあらためてわかったことは、上映作品が参加者数に影響すること。当たり前といえば当たり前なのですが、せっかく参加するならやっぱり自分が興味のある作品を見たいですよね。その一方で、「都合さえつけば、上映作品に関係なく参加したい」という、うれしい声も聞かれました。今回ご参加いただいたママさんも、その半数以上が「
mamaneシアター」に複数回参加してくれているリピーターの方でした。
昨日は、映画を楽しんだ後、ランチ会も開催。ランチ会では、育休ママさんの保育園事情や、2人目3人目の子育てについて、週末にどこに遊びに行くか、母子家庭状態の子育てなど、ママさんならではの話題で盛り上がったと、ママネスタッフから報告がありました。
ママさんの中には、両親や親戚、友だちと遠く離れてこの街に暮らしている方もいます。「
mamaneシアター」や「
ママネ」の活動を通じて、新しいママ友との交流や情報交換の場に、そして地域とつながるきっかけにしていただけるとうれしいです。
『
猿の惑星:新世紀 ライジング』では、人類と、知性を獲得した猿人類の対立という構図の中で、権力は暴走し、戦争はコントロールできないもの…、として描かれています。わたしたちおとなは、未来ある赤ちゃんやこどもたちに平和な社会を残したいものです。