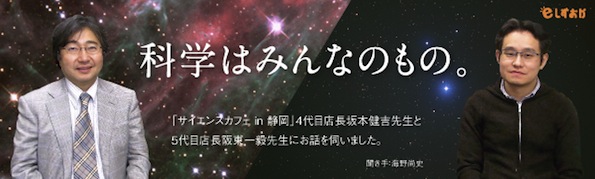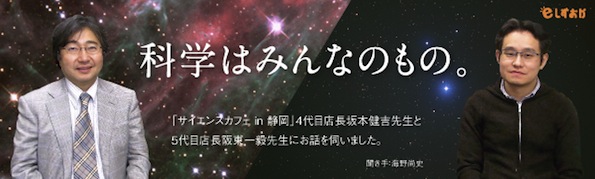 東日本大震災が起きてその約1ヶ月後、
東日本大震災が起きてその約1ヶ月後、
「地震と放射能:いま知っておくべきこと」と題した緊急セミナーが
静岡市で開催されました。地震について様々な情報が錯綜する中で
静岡市民にむけて本セミナーを企画した「サイエンスカフェ in 静岡」。
会場で聞かれた「地震のことがよく理解できた」「安心しました」
という市民の声は、インターネット社会になり多くの情報があるにもかかわらず、
私たちの暮らしの中には自分では取り除くことのできない不安があることの
現れだったように思えます。
放射能、地球温暖化、遺伝子組み換え食品、環境ホルモンに狂牛病etc…、
科学が発達して便利な世の中になるにつれて、
わたしたちの暮らしを取り囲むさまざまな科学的問題。
生活を豊かにしてくれた多くの工業製品や自然に対する素朴な疑問と、
「わたしたちの周りで、今何が起きているのだろう」という漠然とした不安は、
科学に触れることで軽減できるのもしれません。
東日本大震災後の緊急セミナーから約1年が経った今、
同セミナーを企画した静岡大学理学部の先生であり
「サイエンスカフェ in 静岡」の4代目店長坂本健吉先生と
5代目店長の阪東一毅先生にお話を伺いました。
・「サイエンスカフェ in 静岡」とは
静岡大学理学部で最先端の研究をしている先生を講師に迎え、 科学の話を地域の人が気軽に聞けるカフェスタイルの場。 過去6年間で、延べ5000人以上の市民が参加。地球温暖化、クローン生物、環境ホルモン、新機能性物質の合成など、社会的に大きな関心を集めている分野から、「ブラックホール活動天体への招待」「アルキメデスの失われた写本を読む」「富士山で見られる南極と北極の世界」「遅い光と速い光」など、科学のロマンを感じさせるお話まで、幅広いテーマをとりあげている。開催場所は、B-nest静岡市産学交流センター。
▶ 坂本健吉さん:静岡大学 理学部科学課 教授 (写真左)
阪東一毅さん:静岡大学 理学部物理学科 講師(同右)
▶「サイエンスカフェin 静岡(ブログ支店)」:
http://sciencecafe.eshizuoka.jp/
▶「サイエンスカフェin 静岡」公式サイト:
http://www.sci.shizuoka.ac.jp/sciencecafe/
▶ 静岡大学理学部公式サイト:
http://www.sci.shizuoka.ac.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◀【1】を読む
【2】 自然科学的なものの見方が助けになる
坂本 それに日本の社会全体が、感覚だけで動いている感じがしませんか。
今の世の中は、ニュース性やおもしろさだけがクローズアップされがち。
話題性があればすぐに飛びつくけれど、
そこでの理解はとても表面的で、内容まで理解されないまま
大騒ぎになることがあります。
海野 少し前ですが、ダイオキシンや環境ホルモンが問題になりましたね。
坂本 マスコミが繰り返し取り上げて大騒ぎになりましたが、
実際には内容を理解して大騒ぎになったわけではないと思います。
誰かが「これは大変問題だ!」といい始めて、騒ぎが騒ぎを大きくする。
海野 でも、のど元過ぎれば…
坂本 新しい問題を誰かが取り上げて騒ぎ始めると、
昨日までの問題は忘れて、そちらに飛びついてしまう。
今では、ダイオキシンも環境ホルモンのことも、
誰も言わなくなってしまいました。
震災の後には、 地球温暖化のことも。
海野 狂牛病もほんの数年前のことですね。
坂本 そんな状況を自然科学者の目で見ると
「本当にそうなんだろうか」
「それでいいんだろうか」と思うことが山ほどある。
ダイオキシンの危険性ひとつとっても、
専門家の中で共有されている内容と、
一般の方の理解に開きはがある。
簡単にいえば、専門家の持っている情報が社会に伝わっていない、
ということです。
上から目線で「啓蒙」したいというのではなく、
専門家として一般の方に知ってほしいことがいっぱいある。
海野 専門家の情報が、ふつうの人の役に立つ。
坂本 それに
「自然科学的なものの見方」が
これからの社会を生きる上で助けになるはずです。
サイエンスカフェが「自然科学的なものの見方」を身につける
きっかけになれば、という思いもあります。
海野 なるほど。
坂本 福島の放射能の騒ぎひとつとっても、いろいろな意見があります。
今はTwitterやフェイスブックなど、いろいろな情報発信の
ツールがありますから、声の大きな人の意見が影響力を持ちやすい。
リスクはどこにでもあるんです。
何かを判断する時に、感覚だけにたよるのではなく
「数値化」して判断できることは数字で客観的に判断することが大事です。
海野 話題に踊らされてしまったり、新しい事件が起こると
そのことはすっかり忘れてしまったりすることはたしかにありますね。
しかも、話題の賞味期限は年々短くなって、
情報の消費スピードだけが早くなっている。
海野 判断に迷ったときはどうすればいいのでしょう?
坂本 難しいですね。
できることといえば、ひたすら調べることでしょうか。
ただし、結果として真逆の意見にぶちあたることがある。
そしたら、今度はそれぞれの意見の背景を調べる。
インターネットは便利ですが、断片的な情報が多い。
一般的には書籍の方が信頼性が高いと思います。
もっとも、変な本も多いので1冊だけを信じすぎないこと。
海野 インターネットでは、自分の信念を補強してくれる情報に
集中的にアクセスしがち。
自分の信念を強化するだけの場合もありますからね。
・ ・ ・
【1】そもそも何の目的で始まった?
【2】 自然科学的なものの見方が助けになる
【3】「宇宙」「富士山」「化石」が人気
【4】地震と放射能の話は、静岡での生活と切り離せない