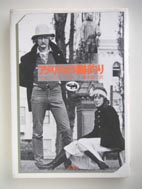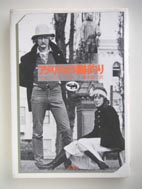昨日は編集部Uの送別会&「K-MIXスキー&スノーボードマガジン」の
打ち上げ。
お酒の席で、先日このブログで書いた「落語が、来てる」の話に続き
「今、何が来てるか」という話題に。
その場では思いつきでテキトーに答えてしまいましたが
(その場にいたみなさん、すみません)、ここのところ
わたしが勝手に「来てる」と思っているものがあります。
それは日本ではカウンター・カルチャーの騎手?として70年代後半に
人気のあった作家・詩人「リチャード・ブローティガン」。
本人は84年に自殺してすでに亡くなっています。
http://www.asahi-net.or.jp/~IF2N-SZK/rb.html
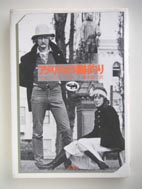
代表作は「アメリカの鱒釣り」。「そういえば10代後半か20代前半に
読んだな」と思った方は、ほとんどが40代以上ではないでしょうか。
80年代後半から90年代にかけてのブローティガンは、新しい人たちに
読まれることもなく、ほとんど忘れられた存在だったように思います。
雑誌などで表立って取り上げられているという話は聞いていませんが、
その「ブローティガン」がここのところあちこちで登場しています。
■「ブローティガンが(じわじわと)来てる」らしい勝手な理由
その一 ブローティガンの翻訳本を数多く手がけた藤本和子が
2002年新潮社から「リチャード・ブローティガン」を出版
(ことの発端はここから始まったと思うのが妥当ですね)
その二 古本の世界でブローティガンが動きはじめた
2003年、フリーライター岡崎武志が「古本極楽ガイド」(ちくま文庫)
のなかで「トウキョウのブローティガン狩り」と題して、
東京中の古本屋の棚からブローティガンの本が急激に消えはじめている
(要は手に入りにくくなっている)と報告している
その三 新しい人たちの間でブローティガンは復活(再発見)しつつあるのでは
2005年2月に出た松浦弥太郎(COW BOOKS代表)のエッセイ
「くちぶえカタログ」の中で、彼自身がここ数年
ブローティガンの痕跡を求めて(彼の本をたどって)
サンフランシスコにばかりに行っていると告白
その四 2005年5月に出た角田光代の新刊「この本が、世界に存在することに」
の中の短編「手紙」の中にも「ブローティガン」が登場。
三十五歳の主人公がブローティガンの詩集「東京日記」を手にしながら
「この詩集を買ったのは二十歳をいくつか過ぎた頃」と語っている。
(角田光代とブローティガンはまったくつながらなかっただけに
彼女の本での登場は個人的に印象が強かった)

その五 2005年8月 新潮社が「アメリカの鱒釣り」を文庫化決定
その六 2005年11月 ちくま文庫より「ビッグ・サーの南軍将軍」文庫再登場
戸田書店本店の新刊コーナーでさりげなく面だしで陳列されている。

そして 「ビッグ・サーの南軍将軍」のあとがきで翻訳者の藤本和子が
「ブローティガンの再登場がこうして度重なる『今』という時期は
どういう時期なのだろうか。(中略)…何かが起こりつつあるのか」
と、「ブローティガン」と「今」について「けっして偶然ではない」
と語っている。
とまあ強引ですが、ブローティガンとの最近の出会いの事例をいくつか並べてみました。
今年の初めに岡崎武志の「古本極楽ガイド」で、久しぶりにブローティガンの
名前を思いだし個人的に懐かしがっていたのですが、それ以来、
店頭で、いろんな作家の本の中で、立て続けに接する機会が増えています。
これはここ20年ほどなかった現象。
藤本和子氏がいうように「ブローティガンの再登場が重なる『今』という時期は
何かが起こりつつあるのか」どうかわかりませんが、
すくなくとも、これを機にブローティガンの作品にはじめて接する若い世代の
読者が、30年前の読者とどう違う反応を示すのかは楽しみです。
そうなればきっとどこかでだれかがとりあげることでしょう。
というわけで「ブローティガンが、来てる」といわせてください。
ただし、人知れず水面下で…。
ブローティガンにはそれが似合ってます。