 新宿副都心
新宿副都心と言えば、国内でも有数の超高層ビル街。その中にあってゴシック風のひときわ目立つシンボリックな高層ビルが丹下健三氏設計による
東京都庁舎です。この都庁舎を建てるにあたって、超高層ビル案を前提としたコンペに低層案で挑んだ磯崎新の新都庁舎案の生まれる過程をドキュメンタリー風にまとめた一冊が『
磯崎新の「都庁」』(平松剛=著、文藝春秋)です。幻に終わった磯崎新の新都庁舎案と、戦後日本最大と言われる公共建築コンペの背景に興味を惹かれて、久しぶりに建築の本を読みました……▼
「
Google ブック検索」をめぐる集団訴訟で、昨年10月に和解している全米作家協会と全米出版社協会のメンバーが来日。日本文芸家協会など著作権者団体や文化庁著作権課などに、和解案内容について説明をおこないました。
これをうけて、4月にグーグルに対して
抗議声明を出したばかりの日本文芸家協会の三田理事長は「
グーグルのデータベースからの削除を撤回」(Asahi.com)し、今後は「協力したい」と歩み寄る姿勢をみせたようです……▼
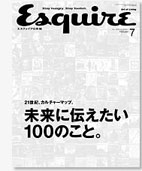
ふと気がつくと、会話の中で雑誌の話題がでるのは、自分と同世代か、少し上の世代の人との間だけになってきたような…。今日は、プロデューサー業を生業としているK氏(K氏も一回り上の世代)の口から『
エスクァイア日本版』も休刊しちゃうみたいだね、どうして?」という話題になりました。
『
エスクァイア日本版』は、僕自身も20代後半から30代にかけて、よく買っていた雑誌。 創刊号を読んで編集部に送ったハガキ(当時メールなどはなかった)の中のコメントが『エスクァイア日本版』の新聞広告で使われ、記念品をいただいたこともあります(笑)。そんな、個人的にも思い出のある雑誌が休刊するようです……▼

「
womo静岡版」は、おかげさまで創刊4周年を迎えました。
毎号「
womo」を楽しみにしていただいている読者のみなさま、そして、お店の情報発信メディアとして「
womo」をご利用いただいているお客さまへ、いつも「
womo」をご愛読&ご利用いただきありがとうございます。4周年記念号は、こんなに派手やかな「
womo」らしい表紙になりました……
弊社主催でビジネスブログ講座を開催しました。今回は、飲食店様向けのブログ講座ということで、飲食店ブログの成功事例や、セルフプロモーションとして効果的な〈
eしずおかプレスリリース〉の書き方・〈
eしずおかカレンダー〉の活用法などについて学びました……▼
6月25日、磐田市にオープンするショッピングパーク「
ららぽーと磐田」さん。オープンを前に
eしずおかブロガーさんが、「ららぽーと横浜」を一足先に体験したレポートを報告してくれています……▼

4月に読んだ
濱野智史(情報環境研究者)の著作『
アーキテクチャの生態系』の中で「環境管理型権力」という概念にであったところに、東京都足立区が21日から若者だけに聞こえる「モスキート音」で、公園にたむろする若者を撃退、という
新聞記事が……▼
弊社のOGで3年ほど前から伊豆・下田で暮らしているNさんが編集する手づくりの雑誌『なかばしまぐらし伊豆』が創刊されました。仕様や価格、販売方法等について、Nさんから相談をうけた(というと聞こえはいいですが、正確に言えば蕎麦を食べながら、いいたいことを言わせていただいただけであります・笑)雑誌ということもあり、私自身もうれしい気持ちで創刊号を読みました……▼
今朝の朝日新聞、日経新聞によると、
ブックオフ株を大日本印刷、講談社、小学館、集英社などが取得方向で協議しているようです。大手出版社×大手書店×中古書流通×印刷会社(大日本印刷はすでに、印刷会社というより情報システム会社かもしれません)連合で、どんな出版流通システム、さらにはコンテンツ流通システムのグランドデザインを描いているのでしょうか……▼
一年前に「
『広告批評』30年の区切り」でも取り上げましたが、雑誌『
広告批評』が4月号で最終号となりました。社主の天野祐吉氏も、
自身のブログで「餞別の味」として取り上げています。
わたしの手元にある一番古い『広告批評』は、1983年の5月号。
(83年というのは、わたしが社会人1年目)
特集は「パルコってだれだ?」。
石岡瑛子のロングインタビューのほか、「パルコとわたし」と題して、
アートディレクターの
浅葉克己氏や「
ほぼ日」の糸井重里氏(当時はコピーライターですね)、
そして作家の橋本治と林真理子氏にも取材しています。
1883年7・8月号では「マンガ形式による現代文化論」、
10月号「浮世床メディア論」、
11月号「生活が消えた?」、
を特集している。
こうして特集のテーマや紙面に登場している人選を振り返ってみると、
「広告批評」が初期の頃から広告の世界を幅広く定義して編集してきたことがわかります。
同時にそれは、80年代が広告が社会にたいして多くの影響を及ぼしはじめた時代背景と
重なっていた、ともいえるのでしょうね。
最終号では「クリエイティブ・シンポシオン2009」という「広告批評」のイベントを誌上再録しています。
テーマとキャスティングをいくつか紹介してみますがここからも、広告を通して社会を浮き彫りにするという
「広告批評」が一貫して取り組んできた編集方針が、
そして、編集兼発行人の島森路子氏の言葉を借りれば
「広告は時代の映し絵であり、
人間そのものの映し絵でもある」
という編集者の強い意志が、伝わってきます。
『
広告批評』最終号より(一部抜粋)
・「アートとデザインのあいだ」
佐藤可士和 × 村上隆
・「隠居は青春宣言だ」
横尾忠則 × 一青窈 × 天野祐吉
・「ネット空間に浮遊する映像と身体」
辻川幸一郎 × 児玉裕一 × ピエール滝
・「テレビとインターネットの未来」
宇川尚弘 × 倉本美津留 × ひろゆき
・「私を作った広告写真」
副田高行 × 藤井保 × 秋山具義 × 辻佐織
・「宇宙から見た女と表現」
森本智恵 × 大宮エリー × 佐治晴夫
・「歌とボクらとコマーシャル」
箭内道彦 × 斎藤和義
・「広告の原点にもどるということ」
大貫卓也 × 谷山雅計 × 天野祐吉
・「ブランドは個人を表現する」
秋山晶 × 岡康道 × 服部一成
・「意味と無意味の間で」
谷川俊太郎 × 高橋源一郎 × イッセー尾形 × 天野祐吉
テレビやラジオで流れはじめている
忌野清志郎追悼特番に接して、随分と久しぶりに本棚から彼の書いた『瀕死の双六問屋』(忌野清志郎著、光進社)を取り出し、読み返す……
『CODE』(山形浩生・柏木亮二訳/翔泳社、2001年)、『コモンズ』(山形浩生訳 翔泳社、2002年)の著者で、オープンソースの擁護者として知られる
ローレンス・レッシグ教授の最新著書『Remix』が、5月1日からPDF版を無料でダウンロードできるよう公開されている……▼
今年のゴールデン・ウィークは、すっかりアカデミー賞ウィークになってしまった。シネ・ギャラリーで上映中の第81回米国アカデミー賞ノミネート・受賞作品『スラムドッグ$ミリオネア』『ミルク』に続き、今日は『フロスト×ニクソン』を観る……▼
もちろん、憲法記念日にあわせて公開されたわけではないと思いますが、映画『
ミルク』を見ながら、……思い出したこと▼

 新宿副都心と言えば、国内でも有数の超高層ビル街。その中にあってゴシック風のひときわ目立つシンボリックな高層ビルが丹下健三氏設計による東京都庁舎です。この都庁舎を建てるにあたって、超高層ビル案を前提としたコンペに低層案で挑んだ磯崎新の新都庁舎案の生まれる過程をドキュメンタリー風にまとめた一冊が『磯崎新の「都庁」』(平松剛=著、文藝春秋)です。幻に終わった磯崎新の新都庁舎案と、戦後日本最大と言われる公共建築コンペの背景に興味を惹かれて、久しぶりに建築の本を読みました……▼
新宿副都心と言えば、国内でも有数の超高層ビル街。その中にあってゴシック風のひときわ目立つシンボリックな高層ビルが丹下健三氏設計による東京都庁舎です。この都庁舎を建てるにあたって、超高層ビル案を前提としたコンペに低層案で挑んだ磯崎新の新都庁舎案の生まれる過程をドキュメンタリー風にまとめた一冊が『磯崎新の「都庁」』(平松剛=著、文藝春秋)です。幻に終わった磯崎新の新都庁舎案と、戦後日本最大と言われる公共建築コンペの背景に興味を惹かれて、久しぶりに建築の本を読みました……▼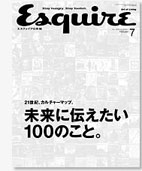 ふと気がつくと、会話の中で雑誌の話題がでるのは、自分と同世代か、少し上の世代の人との間だけになってきたような…。今日は、プロデューサー業を生業としているK氏(K氏も一回り上の世代)の口から『エスクァイア日本版』も休刊しちゃうみたいだね、どうして?」という話題になりました。
ふと気がつくと、会話の中で雑誌の話題がでるのは、自分と同世代か、少し上の世代の人との間だけになってきたような…。今日は、プロデューサー業を生業としているK氏(K氏も一回り上の世代)の口から『エスクァイア日本版』も休刊しちゃうみたいだね、どうして?」という話題になりました。