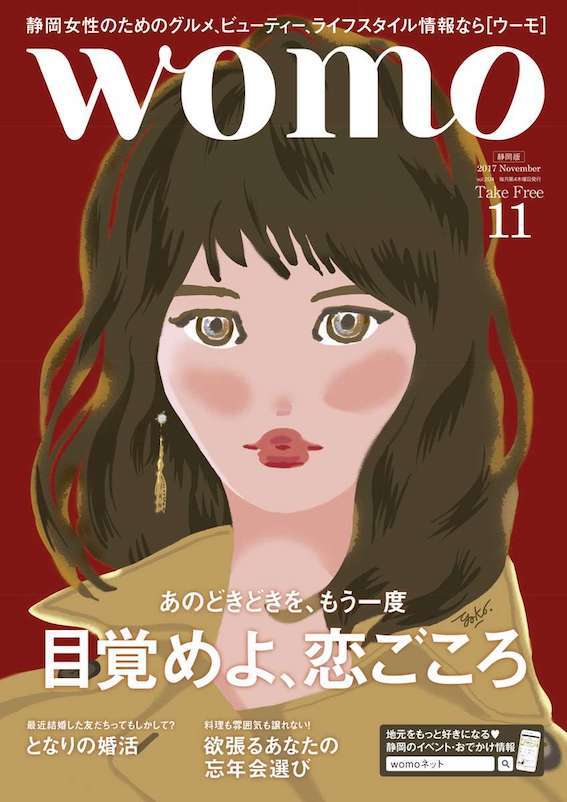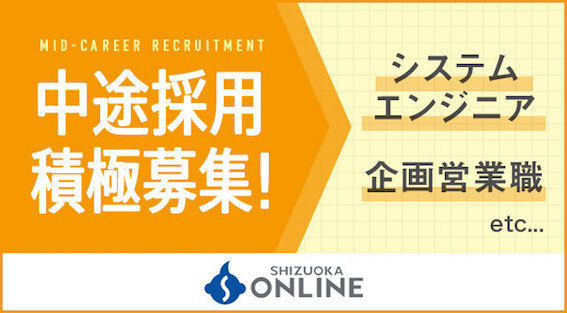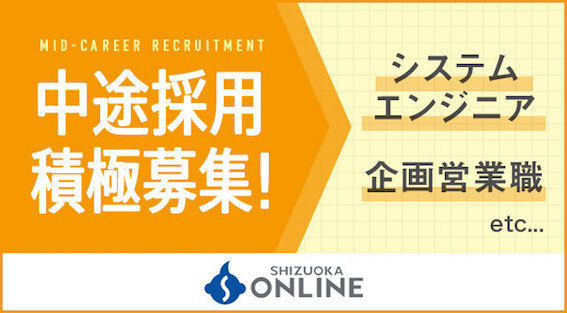今週から始まった静岡県立大学大学院社会人講座「地方創生の評価と展望」。「増田リポート」の消滅可能性都市の衝撃から3年が経過。国も地方行政も最重要課題として掲げている「地方創生」の取り組みの進展は、地方に暮らす市民としては気になるもの。しかし、テーマが大きすぎて、自分一人ではなかなか手がつけられません。そんな中、地元大学の第一線の研究者のみなさんに、まとめて解説していただける機会はとても貴重。
静岡県立大学経営情報イノベーション研究科特任教授の西野勝明先生によれば、地方創生の評価指標は、人口流出の抑制効果と県民平均所得の2つ。地方創生加速化交付金の交付対象事業と評価指標との関連性については曖昧とのこと。地域分析システム「RESAS」の有用性は評価高。
藤本健太郎先生による少子化対策の講義では、地方の行政間で生産年齢人口の奪い合いをするよりも、行政と市民が危機感を共有し、長期的な視点に立ち自然増につながる施策を行うことが重要とのこと。まずは、地域で恋する機会を増やすこと?
『
womo11月号』の特集は、「
目覚めよ!恋ごころ」。微力ながら地方創生の課題解決のお役に立てられればうれしいです。
「womo編集長コラム」特集は「目覚めよ!恋ごころ」
・https://womo.jp/column/detail/27928//
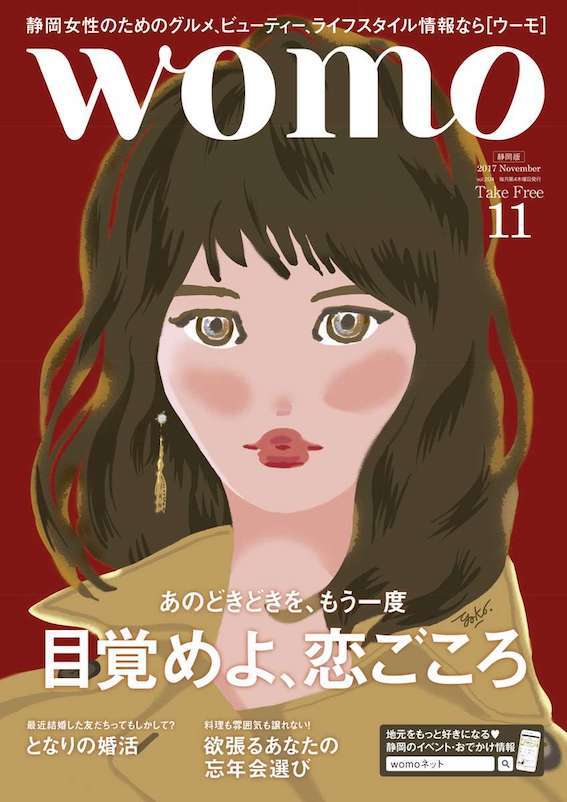
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しずおかオンラインは社員を募集しています。
・しずおかオンライン:採用サイト↓
http://www.esz.co.jp/recruit/index.html
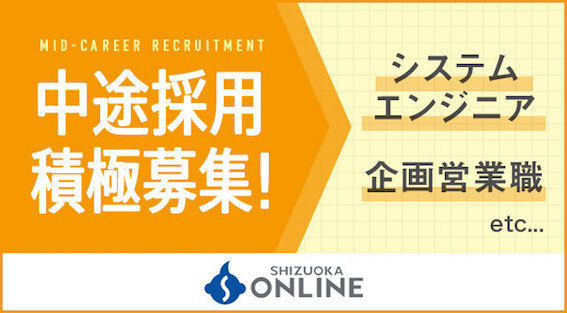
今年の春にオープンした鷹匠3丁目の古書店「
枇杷舎」に、ようやく行くことができました。場所は、つつじ通り沿いのマンションの一室。土曜日の午後4時間だけの営業。
文芸、児童文学、絵本のほか、エッセイなどが中心の品揃え。レジの前には、熊本「
橙書店」の発行する『アルテリ』のバックナンバーも。店主(女性)さんの話では、ご自分の蔵書と友人が持ち寄ってくれた本が中心だとか。
エッセイの棚から伊丹十三の『女たちよ!』(新潮文庫)を購入。本好きの知人の部屋を訪問したような雰囲気の古書店「枇杷舎」。これからどのような書店になっていくのか楽しみです。モールガラスがはめ込まれた入口の引き戸(ドア代わり)が、味わいがあっていい雰囲気。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しずおかオンラインは社員を募集しています。
・しずおかオンライン:採用サイト↓
http://www.esz.co.jp/recruit/index.html
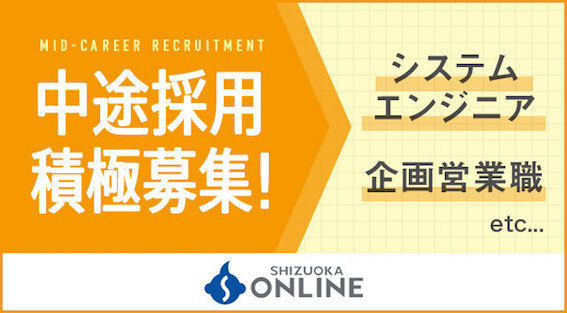
『
ヒップな生活革命』の著者でもある佐久間裕美子さんの新刊『
ピンヒールははかない』(幻冬舎)。NY、シングル、自分の人生を真剣に生きている女性たちの話。
「自由が許されるのは、自分を食わせていけることが前提」「欲しいものがあれば、欲しいと意思表示しなければ、あちらからはやってこない」と前段でおさえた上で、ひと筋縄ではいかない社会の中で頑張っている女性の姿を紹介しています。彼女たちの生き方に触れると、ダイバーシティは自明のこと、性差やワークスタイルも、各人の属性でしかないことに気づかされます。
「女性の君が、自分がどういう人生を送りたいのかをわかっていて、自分の人生の主導権を握れる。そのために勇気の必要な決断をすることができる。素晴らしいことだと思う」「大切なことは自分の道を見つけることなんだ」。これは、恋人と別れることを決めた女性に、彼女の父親がかけた言葉。
NYに暮らす著者は、日本に帰国した折に「幸せだって思われたい」という女性誌のコピーを目にして、「自分の心と付き合っていくだけでも大変なのに、その幸せが他人に紐づいているなんて、なんて恐ろしいことだろう」と思う。そうか、私たちは、他者からの承認が得られないと、自分の選択が正しいのか自信が持てないのか。
本書によれば、「シングリズム」とは「独身主義」ということではなく、独身者が社会から受ける差別を意味するのだそうです。シングル=不幸、パートナーがいる=幸せ、のような風潮はアメリカ以上に日本で強い。「私たちの周りにはたくさんの呪いがある」といった(みくりの伯母)百合の台詞が思い出されます。佐久間裕美子さんからのメッセージは「 You have to stand up for yourself. 」(自分のために戦える人になれ)。百合からは、逃げるが…?
NYセントラルパークで見かけた、公園内で挙式するカップル。参加者は総勢9名。佐久間さんによれば、公園の管理事務所に集会届けと25ドルを支払えば結婚式をあげることができることのだそうです。


アメリカ初の有人宇宙飛行に貢献した3人の女性の物語、映画『
ドリーム』(@
静岡シネ・ギャラリー)を観てきました。満席。数学者、エンジニア、マネージャー。それぞれ得意とする力を発揮して、成果を出しながら周囲の信頼を得、既存のルールを(前向きに、したたかに)乗り越えていく姿勢がすばらしい。
そんな彼女たちの可能性を公正に見極め、機会を与える(責任を引き受ける)上司や裁判官の存在も強く印象に残りました。“ダイバーシティ(多様性)”の必要性が叫ばれる昨今ですが、現場(当事者)と制度が両輪となってこそ推進できるのですね。
正式なNASAエンジニアを目指すメアリー。自分の運命の決定権を持つ裁判官の心を動かす説得力のあるプレゼンテーションが見事。自分が欲しいものを手にしたければ、誰かが与えくれるのをただ待つのではなく、自ら意思表示すること。