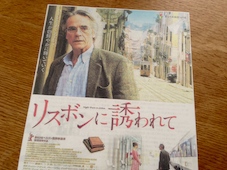横浜・港の見える丘公園の一角にある県立横浜市近代文学館で開催された「須賀敦子の世界展」。文学館の展示は概ね、作家の来歴を年表にしたコーナーと初版本などの作品展示などで構成されることが多い。それらの中で、つい時間をかけて見て(読んで)しまうのが、作家の直筆原稿と手紙の類いだ。
「須賀敦子の世界展」でも、初期の頃の原稿(推敲のプロセスを垣間みることができる)のほか、留学先のフランスやイタリアから両親に送られた手紙や、最愛の夫ペッピーノ宛のもの、それから晩年のものでは、作家で評論家でもある松山巖氏宛の手紙など数多く展示されていて、じっくりと読み入ってしまった。若い頃のしっかりとした意思が伝わってくる筆致が、晩年は角がとれて小さな文字に変わっていく。一方で、ユーモアだけはずっと変わらない。そんな小さな変化を発見できるのも、直筆の手紙を見る楽しみである。作家の手紙ということでは、吉行淳之介が女優の宮城まり子に宛てた手紙も心を動かされるものがある。こちらは、掛川市のねむの木学園の敷地内にある吉行淳之介文学館で読むことができる。
地方で文化・芸術に触れる施設として美術館やコンサートホールなどが話題にのぼることはあっても、地元の歴史や伝統、文芸などを扱う文学館や博物館について語られることは少ない。ひとびとに直接かたりかけることのできる「言葉」を扱う文学館などは、郷土にゆかりのある作家や作品などを通じて、地元の風土や歴史・文化を学ぶ教育的な役割もあると思えるのだけれど。

写真は、1970年に丹下健三氏と東京大学都市工学科都市設計研究室によってまとめられた、「
静清地域広域都市開発計画書」のコピー。
静岡市まちづくり・エリアマネジメント普及啓発推進事業として開催されたセミナー「
丹下健三が描いた“しずおか”の未来像を今読み返す」(主催:静岡市)は、一静岡市民としてなかなか興味深い内容だった。日本を代表する建築家・丹下健三氏が静岡市と清水市が合併する33年も前の1970年に、静清地域の将来像を示した基本計画を描いていたことはまったく知らなかった。それだけに約45年も前に「計画されたもの」を知るよい機会となり、「出来上がった都市」を振り返る貴重な場でもあった。
この計画書の骨子は、静岡駅の南部を東西に走る幹線道路(通称丸子ー池田線)に広い並木道を確保して、静岡都心と清水都心をつなぐ「都市軸」とし、その上にモノレールを走らせるというもの。さらに駿府城公園から登呂遺跡までの地域を都心部として開発し、都市機能を集約。高松や古庄、駒越などの周辺部に高密度の住宅エリアを開発する内容となっている。しかし、そのほとんどは実現されることはなかった。文教エリアとして設定されている有度山麓に、静岡大学、日本平動物園、舞台芸術劇場、県立美術館、県立大学などが建てられたことを除いては。

計画づくりに関わられた東京大学名誉教授の渡辺定夫先生がパネラーとして参加されていて、渡辺先生のコメントからは、当時の計画づくりの様子を聞くことができた。その一方で、本セミナーの主催者であり、丹下健三氏にこの調査を委託した静岡市が、この計画書をどのように評価し、それ以降の静岡・清水の都市計画に活かしたのか、活かさなかったのか、を聞くことができなかったのは残念である。静岡市(行政)の立場からの振り返りこそ、市民に伝えてほしいものである。(渡辺定夫先生によると、丹下健三氏は1960年にも静岡市に都市計画の提案をしていて、この提案は二回目だったとのこと)
とはいえ今大切なのは、これからの静岡市の将来をどのように更新するべきか、を考えることである。パネラーのひとり、東京大学工学系研究会都市工学専攻助教・黒瀬武史氏の「人口減少は一人あたりの空間が広がることでもあり、プラスにとらえる視点も必要」という指摘は新鮮だった。渡辺定夫先生の「地域に今ある資源(ストック)の中から、使えるものを使っていくこと」というストック型社会に通じるコメントは現実的で説得力がある。
おふたりの意見を実現するためには、人口が減る静岡市で豊かさを実感できる新しい生活像をどう描くのか。そのとき、わたしたち自身が、地域の何を次世代にも価値のある資源として認め、どのように活かそうとするのか、が問われているのだろう。

消費税の引き上げ時期が話題になっていますが、少しの期間延期されたとしても消費税が下がるわけではないことを考えれば、私たちにできることは、しっかりと計画的に、ギリギリではなく早め早めに、家作りにとりかかることではないでしょうか。そのための第一歩は、情報収集から。
静岡県西部・愛知県三河エリアで家づくりする人のための情報満載の一冊『
家を建てるときに読む本』静岡県西部・愛知県三河版が発行となりました。
地元工務店各社のイチオシ施工例を集めた特集「2015注目の家」をはじめ、「こどもがのびのび育つ家」「1000万円台の家」「デザイン住宅」「リフォーム事例集」「モデルハウス実例集」など、ジャンル別に紹介しているほか、家づくりの先輩たちのリアルな声を集めた「成功&失敗談53選」や「先輩施主のあるある座談会」なども必見です。
 書店、コンビニで販売中。
書店、コンビニで販売中。
■380円(税込)
■A4変形判・368ページ
■2014年11月20日発売
webイエタテ 「愛知県三河版」
http://www.sumailab.net/index/mikawa.html
webイエタテ 「静岡県西部版」
http://www.sumailab.net/index/west.html

先日、静岡市初の地ビール醸造所「AOI Brewing」(アオイブリューイング)を開設した
満藤さんにお話を聞きながら、そういえば満藤さんとおなじような話をどこかで聞いたなぁ、と思っていた。それで、思い出したのだけど、それは
『ヒップな生活革命』(佐久間裕美子著、朝日出版社)の中で紹介されている“ヒップ”なひとたちの話。
“サード・ウェーブ”のコーヒーショップを開いていたり、男性のための床屋を始めたり(???だと思いますが、興味ある方は本書で)、ムダを出さない責任ある食べ方を提唱する食料品店だったり、究極の地産地消?ともいえる都会のビルの屋上農園(もちろん有機栽培で、空気の浄化に一役買い、消費は階下の街で)や、エンジニアド・ガーメンツをはじめとしたメイド・イン・ニューヨークの人たちだったり…。
共通しているのは、置かれた状況を理解し、衣食住の習慣を見直し、いま自分の目の前にあることを一つひとつ丁寧に行っていこう、という姿勢。ひとことでいえば、今いる場所で豊かに暮らすための地に足が着いた生活、でしょうか。
「
おいしい手造りビールを一所懸命に造って、地元の人に愛されながら、いつまでも飲み継がれようになれたらうれしい。ぼくは、きっと地元の人よりも静岡を愛してますから」という満藤さんの言葉から、今静岡で一番のヒップな人を連想したのでありました。
※満藤直樹さんのインタビュー記事は、11月の「インタビューノート」(日刊いーしず)で公開します。
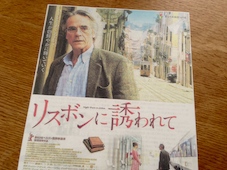
「選ばなかった人生」に思いを馳せるような話は、そのこころの有り様が消極的に感じられて、できれば近づきたくはないのだけれど、今回はタイトルに誘われて、正確には「リスボン」という街の名前の響きに魅かれて、映画『
リスボンに誘われて』(
@静岡シネ・ギャラリー)を観てきた。原作は、スイス生まれの作家、哲学者のパスカル・メルシエの小説『Night Train to Lisbon』(邦題「リスボンへの夜行列車」早川書房・浅井晶子訳)。世界で400万部も売れたベストセラー小説とのことだが、そちらは読んでいない。それでも映画は楽しめた。テージョ川に架かる「4月25日橋」、サン・ペドロ・デ・アルカンタラ展望台からの夕景、石畳、路面電車、路地などなど、古都リスボンの風景が美しい。主人公は“boring”(たいくつな人)と言われて妻に去られ、あなたは“boring”なんかじゃないわ、といってくれる女性にリスボンで出会う。目の前の人が自分の目にどう映るかは、合わせ鏡を見るようなものなのかもしれない。それから映画の冒頭で、主人公が偶然手にした切符を手に、スイス・ベルンからリスボン行きの夜行列車に飛び乗るシーンがある。「
観る鉄」としては、国境を越えて走る夜行列車にも大いに旅情を感じてしまう。