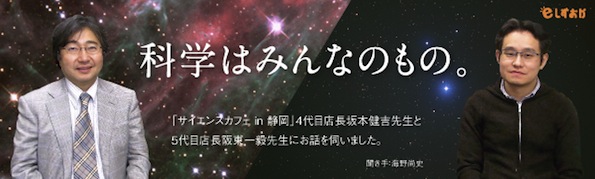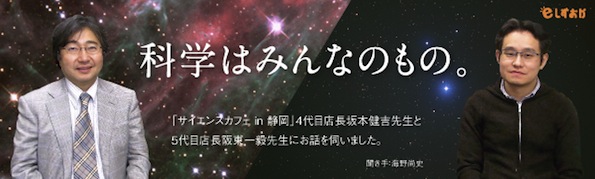 東日本大震災が起きてその約1ヶ月後、
東日本大震災が起きてその約1ヶ月後、
「地震と放射能:いま知っておくべきこと」と題した緊急セミナーが
静岡市で開催されました。地震について様々な情報が錯綜する中で
静岡市民にむけて本セミナーを企画した「サイエンスカフェ in 静岡」。
会場で聞かれた「地震のことがよく理解できた」「安心しました」
という市民の声は、インターネット社会になり多くの情報があるにもかかわらず、
私たちの暮らしの中には自分では取り除くことのできない不安があることの
現れだったように思えます。
放射能、地球温暖化、遺伝子組み換え食品、環境ホルモンに狂牛病etc…、
科学が発達して便利な世の中になるにつれて、
わたしたちの暮らしを取り囲むさまざまな科学的問題。
生活を豊かにしてくれた多くの工業製品や自然に対する素朴な疑問と、
「わたしたちの周りで、今何が起きているのだろう」という漠然とした不安は、
科学に触れることで軽減できるのもしれません。
東日本大震災後の緊急セミナーから約1年が経った今、
同セミナーを企画した静岡大学理学部の先生であり
「サイエンスカフェ in 静岡」の4代目店長坂本健吉先生と
5代目店長の阪東一毅先生にお話を伺いました。
・「サイエンスカフェ in 静岡」とは
静岡大学理学部で最先端の研究をしている先生を講師に迎え、 科学の話を地域の人が気軽に聞けるカフェスタイルの場。 過去6年間で、延べ5000人以上の市民が参加。地球温暖化、クローン生物、環境ホルモン、新機能性物質の合成など、社会的に大きな関心を集めている分野から、「ブラックホール活動天体への招待」「アルキメデスの失われた写本を読む」「富士山で見られる南極と北極の世界」「遅い光と速い光」など、科学のロマンを感じさせるお話まで、幅広いテーマをとりあげている。開催場所は、B-nest静岡市産学交流センター。
▶ 坂本健吉さん:静岡大学 理学部科学課 教授 (写真左)
阪東一毅さん:静岡大学 理学部物理学科 講師(同右)
▶「サイエンスカフェin 静岡(ブログ支店)」:
http://sciencecafe.eshizuoka.jp/
▶「サイエンスカフェin 静岡」公式サイト:
http://www.sci.shizuoka.ac.jp/sciencecafe/
▶ 静岡大学理学部公式サイト:
http://www.sci.shizuoka.ac.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【第1回】そもそも何の目的で始まった?
海野 はじめまして
坂本 こんにちは
阪東 こんにちは
海野 東日本大震災が起きてその約1ヶ月後に開催した
「地震と放射能:いま知っておくべきこと」と題した
緊急セミナーはタイムリーでしたね。
坂本 ありがとうございます。
海野 あれから1年経が経って、「サイエンスカフェin 静岡」も6年目に入りました。
最初は、予算もないところから始めたとお聞きしました。
坂本 「サイエンスカフェin 静岡」は平成18(2006)年12月に、
静岡大学の理学部と創造科学技術大学院の有志によって
オープンしました。中心になっていたのは、
初代店長の小山先生(現早稲田大学教授)です。
海野 そうなんですか。
坂本 予算もなかったので、といいますか、
いまでも予算はないのですが(笑)。
先生方には、いまでもボランティアで参加していただいています。
まるっきりボランティアなので、いつ止めてもいいんです(笑)
海野 ははは…、それは困ります(笑)。
ところで、坂本先生は、いつ頃から関わられたのですか?
坂本 私が静岡大学に着任したのは19年で、
参加したのは平成20年の四月頃でしょうか。
「サイエンスカフェin 静岡」は、実は学内の宣伝には
力を入れていなかったので、
わたしも最初の頃はよく知りませんでした。
海野 …そうなんですか。
坂本 で、しばらくして「なんかやっているな」と気になって…。
何回か参加してみたところ
「教員が聞いても、意外と面白いじゃないか」と思ったわけです。
それからですね、関わるようになったのは。
海野 先生が聞いても面白かった?
坂本 というのは、私たち教員は、同じ学部であっても
ほかの先生の授業を聞く機会はほとんどありません。
それが、サイエンスカフェでは、いろいろな先生方の研究内容を、
ご自分の言葉でわかりやすく聞くことができる。
とても貴重な場であったわけです。
海野 はい。
坂本 着任した頃は先生の知り合いも少なかったので、
サイエンスカフェを通じていろいろな先生方と
知り合えるきっかけにもなりました。
海野 阪東先生は?
阪東 ぼくは、平成21年から関わるようになりました。
サイエンスカフェは、店長といっても理学部の役職でもなく、
誰が選ぶわけでもありません。
学部内にしっかりとした組織があるわけではなく、
なんとなく出入りして、おもしろがっている先生たちが
ゆるく集まって運営しているのが実態。
海野 店長はどのように決まるのですか?
阪東 「阪東先生、やってみない?」
「…あ、はい、わかりました」
そんなノリで、わたしも店長になったわけです。
海野 そもそも「サイエンスカフェ」の目的は?
坂本 静岡大学理学部が取り組んでいる研究内容を
地域社会に発信することが当初の目的でした。
工学部はカタチとしてみえる「モノ」を作っていますし、
農学部は「作物」というように、研究内容が一般の方にも伝えやすい。
でも、基礎研究などに取り組む理学部の研究内容は、
ふつうの方にはわかりにくいんですね。
阪東 各店長によっても、多少スタンスが違うかもしれないです。
坂本先生の目指すサイエンスカフェと、
ぼくの目指すサイエンスカフェでも、違うかもしれない。
海野 初代店長の小山先生は、どんなことを目指していたんですか?
坂本 小山先生が始めた当時は、基礎科学に与えられる国の予算は
どんどん削られる傾向にあって、危機感が強かった。
あの「はやぶさプロジェクト」ですら予算獲得のために、
どんな経済効果があるのかを示すように求められる時代ですから。
海野 事業仕分けの対象になってしまう?
坂本 基礎研究の重要性を示すためには、市民を味方につけることが
必要だったのだと思います。
それは、いまではますます重要になっています。
海野 坂本先生ご自身は、どんな思いを込めている?
坂本 私自身は、小中学生の頃、近くの大学で催された
イベントに参加したことが科学との出会い。
「科学っておもしろいな」と子どもごころに感じ、
そこでの基礎科学との出会いがきっかけになって
この道に進みました。
自分が経験させてもらったことを、
今度は自分が社会に還元する順番かなと。
海野 ご自身が店長の時はどんな思いで?
坂本 わたしが店長の時は、中高生の若い世代に向けて、
学校で習っている理科の授業を発展させたら
その先にどんな分野につながっているのかを
わかりやすく伝えよう、と心がけました。
「後継者を育てたい」という思いをサイエンスカフェで
実現できるかもしれない、と。
結果的に、理科の授業の先が見えることで
「理学部は、就職先がないんじゃないの?」
という不安の答えにもなるかな。
海野 後継者を育てるためには、その先が広い世界に
つながっていることを見せてあげることも大切ですね。
・ ・ ・
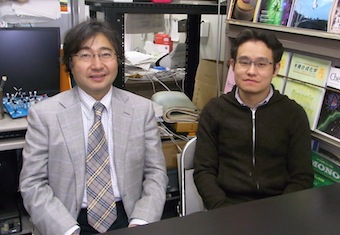
【2】 自然科学的なものの見方が助けになる
【3】「宇宙」「富士山」「化石」が人気
【4】地震と放射能の話は、静岡での生活と切り離せない