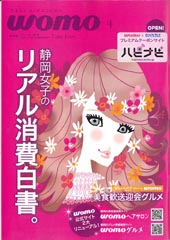今日は、最近ぼくが楽しく読ませていただいているブログをひとつご紹介。
主に句集や詩集を手がけている、東京都調布市の出版社
「
ふらんす堂」代表の山岡喜美子さんの
ブログ。
ほぼ毎日、きれいな草花の写真がアップされ、
文章からは日々の編集の現場や出版という仕事の様子が、
手に取るように伝わってくる。
山岡さんという方に直接面識があるわけではないのですが、
先月朝日新聞に掲載された落合恵子さんのエッセイ「
シーツと市民」について
山岡さんもブログに書かれていて、それ以来の一方通行のおつきあいというわけだ。
「右手で朱筆をもってチェックし、左手は受話器をもって会話をし、左足でゲラをおさえ、
右足は地球上の震動をさぐり、心は詩歌の未来をたずね、
頭ん中は営業戦略をフル回転させる…
いったいわたしどうなってんの状態」で
働く様子
月末には、通帳の0の数字に一喜一憂しながら
「地震や寒さに震えるだけでなく、銀行残高数値にも震えなくてはならない」
小さな出版社を経営することの
ドキドキ感
そしてスタッフとの
春の夕べの一場面や、
作家さんとのお付き合いなどなど…編集の現場が日々綴られている。
山岡さんの意思のある文章も気持ちいい。

昨日は、指物家具「
吉蔵」さんの工房を訪問。今月31日まで開催している「
吉蔵工房市」を見学。展示会には時々寄らせていただいているが、工房を訪ねるのは「
ブログる人々」の取材以来なので約2年ぶり。
といっても「
eしずおかブログ」でご主人が書かれている「
kittsan流」をいつも楽しく拝見しているので、私自身は「吉蔵」さんのことを身近に感じている。
「吉蔵工房市」では、和家具のほかにも、陶器・織物・アクセサリーなどの小物が数多く展示されていて、女性のお客様には人気のようです。
工房を見学させていただいた後、今回の震災のこと、原発のこと、家具のこと、仕事のこと、ブログのこと、ツイッターやフェースブックなどなど、ご主人からいろいろなお話を聞かせていただく。話題が豊富で、つい長居してしまう。
「吉蔵工房市」には、市内だけではなく、名古屋や東京などの遠方からもお客様が来て、家具を買っていくのだそう。みんな「吉蔵」ファンのお客様。
一昨日、社内勉強会で「顧客満足(CS)」について学んだのですが、 「吉蔵」さんは
ブログやツ
イッターを活用した情報発信も積極的で、お客様に「事前期待」をしっかりと作っている。ご主人や奥様とお会いしてお話していると、家具の魅力はもちろんのこと、お客様の期待を超える対応を、とても自然とされていることに気づく。
それらの「常に変わらない対応」と、和家具の伝統にモダンな感覚をブレンドした、時代とともに「変化する」『吉蔵』の指物家具。お客様の期待に応え、それを超えていくための「CSの実践」が、きっちりとなされている。
はじめて訪問した時と同じように、昨日もご主人とお話していると、奥様が和菓子、お抹茶、しばらくして煎茶をだしてくれた。他ではなかなか体験できないそんな接客も、お客さまにとっては新鮮でうれしいもの。それになによりも、お茶が本当においしいのだ。(静岡に暮らしながら、「お茶が美味しい」と感じる場面はどれだけあるだろう?)
わたし自身はこのところ「断捨離」モードに入っているのですが、「吉蔵」さんの指物で、いつか時期が来たら購入したい品がある。わたしも確実に「吉蔵」ファンになりつつある。
吉野からの帰りの電車の中で、島森路子のインタビュー集2「
ことばに出会う」(天野祐吉作業室)を読了。
先週読んだ「
ことばを訪ねて」の下巻にあたる。インタビュー集2には、『スプートニクの恋人』を出版した直後の村上春樹から、「吉祥招福繁昌描き下ろし」という展覧会を開催した後の横尾忠則まで、11名へのインタビューが選ばれている。
「自分が悪人であることの記憶が、自分を支える。私は、敗北の力に支えられて生きてきた」と語る鶴見俊輔。9.11の後、米軍が進行する直前にイラクを訪ね「非戦」について語る池澤夏樹、「日本国憲法第九条」の特集に登場した映画監督是枝裕和、CMプランナーからSFCの教授に転身した佐藤雅彦の教育論など、人選もテーマもさまざま。
中でも最初に登場する村上春樹のインタビューでは、彼の文体に対する考え方から、「小説に関してのロールモデルは、ジャズのマイルズ・デイビス」と語らせるなど、貴重なインタビューとなっている。少し長くなりますが村上春樹のインタビューから一部抜粋して紹介する。
僕は、できるだけ健全になろうと思っている。健全になればなるほど、対比的に一種の暗闇とか、そういうものが深くなっていくから、それを突き詰めていこうと。そして、なるべく単純なわかりやすい文章で、深くて複雑でわかりにくいものを書く。 ただ単純なだけじゃ人は読まないから、そこには芸が必要で、それに関しては、僕は人を惹きつけるための文体を自分で作っていったんです。
文体というのは、麻薬と同じなんだよね。一回注射しちゃうと離れられなくなる。その文体なしでは生きていけなくなる。だから、僕は文体というものをすごく大切にしていて、行くとこまで行って、ここで変わっていいと確信するまでは、簡単に変えたりしない。
1960年代の終わりの、いわゆる政治の季節には、「人民」とか「革命」といった言葉が氾濫していたけど、そうした言葉は観念にしか過ぎなくて、人びとの本当の地平というものは見えていなかった。そうした状況が僕に言葉というものに対する不信感を持たせて、その結果、より個人的なところに立って、どんどん穴を掘り下げながら小説を書いていくことになった。ただ、そういう時期が一回転した、という感じはあったかもしれない。
創作意欲というか、書くべきある種のマグマみたいなものがある。自分の中に燃料のコアみたいなものがあるのはわかっている。だから、それが発火点に達するのを待てばいい。
小説に関して先生のような存在はいないんだけど、ジャズのマイルズ・デイビス、彼が僕のロールモデル。つねに後ろは振り返らず、新しいものをインテイクし、それを煮詰め、煮詰め切ったところで新しいインテイク…新しいものの取り入れ方のダイナミックさとネジの締め方の厳しさが素晴らしい。
『ノルウェイの森』があれだけ売れたあとは、すべてがいやになってしまった。生きていくのがいやになるくらい。一番いやだったのは、それまでなんでもなくつき合っていた人たちが、なにか妙に離れていったり、よそよそしくなったり、裏切ったり…があったこと。そういう人間関係の変質みたいなものが、すごく辛かった。それは僕にとっては大事なものだったから」
そして、あとがきでは橋本治が、「島森みちこさんのこと」と題してこんな文章を寄せている。
島森路子というインタビュアーのすごさが見えにくいのは、彼女がインタビュアーとしての自分の姿を平気で抹消してしまうからである。彼女を相手にして喋って、それが原稿化された時、私の場合、それに対して合いの手を入れた彼女は存在していない…原稿のかなりの部分に「聞き手の島森路子」は存在するのに、存在しながらも見えない。
「『広告批評』と付き合うことによって、自分は成長してしまったな」と思うのは、インタビュアーとして存在していた島森さんの受容力がとても大きい。
「受容する知性」という、見えにくいがしかしとんでもなく重要なもののあり方を、私は島森路子という人を通して理解したと思っている。それは私だけではないと思う。島森さんにインタビューされた人は、みんな島森さんにインタビューされたことを喜んでいると思っている。

村上春樹 物語はいつも自発的でなければならない
鶴見俊輔 自分を根底から支えるもの
池澤夏樹 反戦の楯としての広告
是枝裕和 「九条」を手がかりに日記を描いた
深澤直人 日常感覚の中にデザインの必然がある
佐藤雅彦 本当に面白いことは何か
浦沢直樹 現実がマンガを追いかけてくる
とんねるず おれらはニッポンのブルースブラザーズだ
爆笑問題 十年間ケンカしっぱなしです
ラーメンズ 面白いことは向こうにある
横尾忠則 福を呼んでこそ広告だ(展覧会にて)

天気予報によれば今週末はよく晴れるということだったので
思い立って、吉野山へ行ってきた。
「お花見に」と言いたいところだが、吉野山の桜の見頃は4月中旬からGW。
とはいえ、少しは期待しないわけではなかったのですが
「今年はまだだねぇ。去年は、今頃は少しは咲きはじめていたんだけど」と、
竹林院横から奥千本入り口まで連れて行ってくれるシャトルバスの運転手の弁。
あと2週間もすれば多くの花見客で賑わうであろう
金峯神社から西行庵にかけての山道はとても静かですれ違う人もない。
20分ほどかけて山を登り、奥千本に近づくと
桜どころか、まだところどころに雪が残っている。
途中、西行や芭蕉も立ち寄ったといわれる苔清水で喉を湿す。
苔清水のすぐ先が、西行が3年間過ごしたといわれる小さな庵だ。
深い山間のまだ眠ったままの奥千本の桜が満開になる様子を想像しながら
山を下り、高城山、吉野水分神社に寄り道しながら
今日一日のんびりと散策を楽しんだ。
シャトルバスの運転手によれば、この春は、
関東方面のお客さんの多くがキャンセルしてしまったとこぼしていた。
吉野の山にも震災の影響が出ているようだ。
震災の報道を見ながら、地震・津波の恐怖や不安、そして少しずつ芽生える希望などを、遠くの人々の心にも届かせる力は、コメンテーターや専門家の解説にあるのではなく、被災者自身の生の言葉なんだ、ということを日々実感。
週末から、昨年出版された島森路子のインタビュー集1『
ことばを尋ねて』(天野祐吉作業室)を読んでいる。「
広告批評」の創刊号から終刊号までの30年間の間に、島森路子(2代目編集長)がインタビューした200名を超す人の中から選ばれた24編を上下刊の2冊に収めている。
いずれも、インタビューアーとして定評の高い島森路子さんの代表的な文章。どのインタビューも単に興味深く読めるというだけではなく、内容も文体も、時代を感じさせることなく、つい最近インタビューしたかのように新鮮に読むことができることにあらためて驚く。
私自身は、島森さんの文体は「話し言葉の衣をかぶった書き言葉」ではないかと思っている。なめらかで推進力のある文体と、絶妙なタイミングで入る彼女の言葉がいいリズムとなって背中を押す役割を果たしている。
もうひとつ、彼女のインタビューの魅力は、対象者の人間としての本質を露にするために放たれる彼女の言葉とその姿勢。彼女の言葉は、つねに、やわらかく深く対象に切り込んでいく。
取材対象者はなんらかの仕事で注目されている時期に登場していただくことが多いのだと思うが、目の前の注目されている仕事の表層的な側面ではなく、その背景の、それを成している人物の人間形成の過程であったり、出自であったり、生き様…などを浮き彫りにしていく。
淀川長治にとって「映画」とは何か、なぜ最後まで結婚せずに独り身を貫いたのか、最高の贅沢と最低の貧しさ、苦労の連続が彼の人間形成にどう影響したのか。
幸せかどうかなんてヒマな人間が考えること。居心地が悪ければ人は動き出す。動けば自分に何ができるかわかり、自分のできることを使って、やりたいことをやる。社会というのは、そういう意味で案外広くできている…と語る養老孟司。
矢沢永吉やジュリーの作詞をし、これから西武百貨店のコピーを書き始める頃の糸井重里。「カッコよさに甘んじてはいけないよ」「権力のアカみたいなものをコソギ落とせるような毎日でなかったら、絶対やられちゃう」と語る32歳の糸井重里の「言葉論」や、学生運動、権力・自由に対するスタンスが、一人語りで語られている。彼が30代前半で書いた「ペンギンごはん」は、30年後の「ほぼ日刊イトイ新聞」にも通底しているということもインタビューを読みながら感じられる。
そして特集「人はなぜホモになるのか」(92年8月号)に登場した三輪明宏のインタビューでは、ホモセクシャルに対する偏見と闘い続けた彼の生き様が赤裸々に語られている。幼少時代の友人の自殺やファッションをメッセージの道具として使わざるをえなかった事情、社会に対する怒り。
「なぜ私がこうしたメッセージをあえて一人で言っているのか、なぜ、いままで一人でやってきたのか…。ひとり一人は全員違う。それが二人三人と集まると、集団自体が個人を離れて、別の人格を持ってしまう。それが、恐ろしいの」と語る三輪明宏。
インタビュアー島森路子が対象者から引き出す言葉は、それぞれの生きることの本質につながり、それらは今読んでも生々しい。同時に、こうしてまとめられたインタビュー集を手にしながら『広告批評』という雑誌の射程の広さと深さ、そしてこの雑誌がいかに稀有な雑誌だったかということにあらためて気づかされた。
長期病気療養中という島森路子さんの早期回復を願う。そして、いつか彼女自身がインタビュイーとなった記事を読んでみたいと思う。その時のインタビュアーは誰が適任だろう?天野祐吉氏、それとも島森路子自身?
手にしてわかる丁寧な造本と派手ではないけど華やかな(まるで島森路子さんのよう)美しい装丁を手がけているのは、菊池信義氏。この本を編集した
天野祐吉氏の島森さんに対する深い想いが伝わってくる一冊。

淀川長治 二十一世紀への遺言
山田風太郎 いつも列外にいるつもりで生きてきた
吉田秀和 音楽の退屈
養老孟司 人間が幸福になる方法
美輪明宏 男は弱いもの、だからいとおしい
谷川俊太郎 老いをどう生きるか
糸井重里 権力の垢をソギ落とすのが感性だ
橋本治 橋本流独断江戸哲学講座巻一
タモリ タモリはかく語りき
ビートたけし おいら下町のワルガキだ
所ジョージ バカみたいなことばかり考えてる
イッセー尾形 舞台に立たないと禁断症状が出てしまう
亀倉雄策 四十三年の軌跡(展覧会にて)
「もしもしグルメ」が【womoグルメ】にリニューアルしました。

「静岡女子&浜松女子のためのグルメサイト」をコンセプトに、
・ランチ情報
・女子会プラン
・記念日プラン
などを充実させていきます。
womoグルメ読者限定の「womoグルメ限定メニュー」も、ぜひチェックしてみてください。
オープンしたばかりの【womoグルメ】。
随時、パワーアップしていきますので、どうぞお楽しみに。
携帯用サイトはこちらから
↓↓↓womoグルメ静岡 携帯版↓↓↓

↓↓↓womoグルメ浜松 携帯版↓↓↓

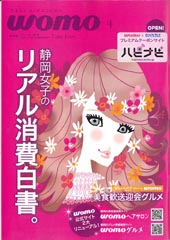

今月の「womo」は、「印刷工場から配送するトラックの手配が困難で納品が遅れるかもしれない」という連絡が入っていたので、ラック設置の日程が遅れることも想定していましたが、なんとかいつも通りに無事納品。今日から静岡、浜松市で「womo4月号」の配布が始まりました。
「womo静岡版」の特集は、
「静岡女子リアル消費白書」。
静岡で暮らすwomo読者のみなさんに消費動向アンケートを実施。
身近な静岡女子の「仕事感」や「遊び方」「お金の使い方」など、
womo世代のリアルなライフスタイルや生活感は興味深い。
「womo浜松版」は、今月プチリニューアル!
新連載の浜ガール的エリア案内では、
「浜松街中板屋界隈」をクローズアップしています。
昼前に久しぶりに散歩にでかける。吉田川に沿って平沢まで歩こうかと思ったが、すぐにコースを変更。県立美術館に向かい、開催中のギッター・コレクション展を見ることに。ギッター・コレクションは、伊藤若冲や白隠、酒井抱一、俵屋宗達など、江戸時代を代表する画家の作品で知られる。
若冲の「白象図」や酒井抱一の「朝陽に四季草花図」も見ごたえあるが、今回はじめて知った長澤蘆雪の「月に竹図」がいい。竹ごしにみえる霞のかかったおぼろ月が、幻想的で美しい。
歌川豊広の「納涼美人図」や国貞の「美人見立士農工商図」などの江戸の風俗を描いた作品には、 杉浦日向子のいう「江戸は、日曜日の日本」(維新は「月曜日の夜明け」なのだそう)が描かれている。山水画や花鳥画もいいが、やはり江戸の日常生活を描いた浮世絵は、見ていて飽きない。
ギッター・コレクション展を見終えて美術館の1階に降りると、倉庫のような四角い箱があり、その中に草間彌生の「水上の蛍」が展示されている。一人ずつその倉庫のような箱の中に入って作品を鑑賞する趣向。事前知識なしに入ったのですが、小さな箱の中には無限に増殖していく空間が広がり、同じく無限に点灯するまばゆい光と相まって、現実空間とは思えない不思議な体験でした。
震災や被爆の報道に想像力を働かせながら、同時に、日常を大切にせよ、という声が聞こえてくる。想像力で何を想うのかは、ひとそれぞれ。想うことを確かなものにしようとするなら、それを日常と切り離してはいけないのだろう。2月の朝日新聞紙上に落合恵子さんが書いていたエッセイ「シーツと市民」の文章の一節を思い出す。
…天気のいい朝、洗濯物を干し終える。
小ぶりの達成感、満足感。
日常の短調で平坦とも思える煩雑なあれこれの上に、
小さな葉ずれや雨上がりの土の匂いが彩となって
成り立っている…
それが人生というもの。
”煩雑や些細”を受け止める感覚が、
ささやかな平和や差別化への思いとつながる。
“煩雑や些細”な生活実感が、
それらと結びついている感覚。
明るい陽射しに、白いシーツが風に揺れている。
私たちしずおかオンライングループでは、2011年3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震の被災者への
災害募金の募集を行うことにしました。スタッフ一同、被災されたすべてのみなさまに、哀悼の意を表しますともに、心よりお見舞い申し上げます。
被害状況の全容も確認できていない状況ではありますが、これからの復興にあたっては、被災地の方々への支援が必ずや必要になることと思います。何とぞ主旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
災害の被害が最小限に抑えられますこと、そして一刻も早い復興を、スタッフ一同心よりお祈り申し上げます。
2011年3月15日
株式会社しずおかオンライン
代表取締役 海野尚史
「ハピナビ」による災害募金の募集
http://hapinavi.womo.jp/
本日、3/11(金)17時30分、「womo」とだいいちテレビがコラボした
プレミアムクーポンサイト「
ハピナビ」が予定どおりOPENしました!
誕生したばかりの「ハピナビ」。
これから毎週、みなさまに喜んでいただけるおトクな情報を
紹介していきますので、どうぞご期待ください。

このところ
ブログで紹介したり、
ツイッターにつぶやきました新しいクーポンサイト
『
ハピナビ』が、本日11日17時30分(予定)にオープンします!!
クーポンサイトはすでにいろいろとありますが、しずおかオンラインが今回立ち上げる『
ハピナビ』は、「
womo」や「
しずおかオンラインの本」の読者のみなさま、「
もしもしグルメ」「
womoビューティー」「
スクナビ」などのサービスを利用していただいているユーザーのみなさまにむけて、いつも気になっていたけど気軽には入れなかった飲食店さんや、高い技術力で勝負しているヘアサロンさん、エステさんをはじめ、地元静岡で品質にこだわって各種商品、サービスを提供しているお店さまの、利用体験のきっかけづくりになれば…と考えてスタートします。
できれば安価に、気軽に利用していただくために、お店様に協力していただき、いつもと変わらないサービスを特別価格で提供していただきます。毎週、新しい商品やサービスが登場していきますので、ご期待ください。
「
ハピナビメール会員」のご登録していただけると、 最新情報をお届けできます。
まだ登録がお済みでない方は、ぜひこの機会に登録してみてください。
↓ ↓ ↓
https://members.womo.jp/hapinavi_mail/index
こちらもぜひご覧ください。
「ハピナビで欲しいものを聞いてみた」編
「ハピナビって?」編
わたしがおつきあいさせていただいている方の中で、最高齢がWさん。70代半ばかな。元書籍販売会社の役員だった方で、いまでも大変な読書家。そのWさんが主宰している集まりが昨晩あり、そこで電子書籍についてお話しさせていただいた。
この集まりには、わたしも年に2回ほど参加させていただいている。昨年は
宇宙科学研究所(ISAS)勤務で、小惑星探査機「
はやぶさ」の広報を担当していた方の「はやぶさの帰還は、どれほど快挙か」という熱のこもった話がおもしろかった。
で、今日は「電子書籍」のお話。「はやぶさ」にはかなわないけど、身近な話題として興味をもって聞いていただけたと思う。参加者は9名、平均年齢は70歳を超えている(たぶん)。わたし的には「電子書籍は、年配の方にどう受け止められているか」を、直接知ることのできるまたとない機会だった。
話を始める前に、これまでに電子書籍といわれるものを見た(「読んだ」ではなくてね)ことがあるか聞いてみたところ、一人をのぞいてみなさん未体験。携帯を持っていない方もお一人いた。「やっぱり読書は紙の本がいい」「いまさら新しい機械の操作を覚えるというのもね〜」と、やんわりと否定的な声が多数。
そんな中で、一人だけ「小冊子をスキャンしてPDFにして、iPhoneに入れて持ち歩いています」という方が。つまり「
自炊」。この方(女性)は、アマゾンの有料会員にもなっているそうで、アマゾンでの購入体験がいかに簡単で、早く、送料無料で便利か、アピールしてくれた(ブランディングの成功例ですね)。やっぱり、世代でひとくくりにとらえてはいけない、いけない。
で、持参したiPadとiPhoneを使って、実際の電子書籍、電子書店、 電子本棚を見ていただいた。反応がよかったのは、文字の拡大や文字の読み上げなどの、実際的な機能。そして、みなさんが想像していた以上に「操作が簡単」ということ。途中からは「これなら、自分にも使えそう」という声に変わっていった。
後半は「電子書籍端末に何冊の本が入るのか」という質問に続いて、「我が家の蔵書をどう処分するか」という話題が一番盛り上がった。
みなさんたいへんな読書家とみえて、家の中の蔵書の行く末について悩まれていた様子。電子書籍端末に蔵書を保管できれば、 どうしてもモノとして残しておきたい本以外は、すぐにでもデータ化したい…とのこと。ここで盛り上がるのは、まったくの想定外であり、今日一番の発見かな。
それにしてもWさんの「昨年新古書店のBOOK ○○○に、軽トラック2台分の本を買い取ってもらって5000円でした。岩波文庫も○○全集もそろっていたのに…」そして
「今は本の行き先がないんです」という一言に一同から大きなため息がもれた(気がした)。

年末に紹介した
【電子書籍版】「静岡ジモトリップ」(発行:しずおかオンライン)の12月末から1月末にかけての販売実績が、電子書店の「
マガストア」さんから届きました。
この1ヶ月間の販売実績は53冊。この数字をどう判断するかは意見のわかれるところですが、ひとついえることは、同じ「静岡ジモトリップ」の本誌(紙版)を販売していただいている書店の販売状況と比較すると、一店舗あたりの販売数ランキングで3位に入る数字。電子書店「マガストア」を一書店一店舗と位置づければ、いきなりランクインということになります。
一方で、販売価格は本誌(紙版)の半額以下(税込み350円)のお値打ち価格ということもあり、電子版のみで制作コストを回収するにはいたりませんし、収益面では「さらに多く販売できなくては利益貢献しない」という判断が働きます。
とはいえ、電子書店での電子書籍の販売はスタートしたばかり。これから試行錯誤しながら、さらに読者の方に届きやすく、購入しやすい流通環境づくりに取り組んでいきます。そして、紙版と電子版のそれぞれの利便性を上手く選択していただくことで、生活に密着した地域雑誌を、日常生活の中でおおいに活用していただきたい。
マガストアさんからのリアルな数字のおかげで、「電子書籍」「電子雑誌」について、ようやく地に足の着いた議論や取り組みができる段階に入ることができそうです。
【電子書籍版】「静岡ジモトリップ」を購入してくれた53名の読者がどんな方か、どんな場面で購入にいたったのか、話しを聞いてみたいところです。
「マガストア」はこちら。【電子書籍版】「静岡ジモトリップ」を購入できます。
↓ ↓ ↓
http://www.magastore.jp/category/?id=20
週末二日をかけて、
梨木香歩の『
家守奇譚』をゆっくりと読んだ。久しぶりにいい読書、いい時間。
近しい人には「このところ物語は読んでいない」と公言していたのですが、梨木香歩という人気のある作家も、『家守奇譚』という作品もまったく知らなかった。お恥ずかしいけど…本当。ある日突然目の前に(出会い頭のようにね)人気の作家と作品が、現れて、自分の中にずっぽりと抜け落ちている世界があることに気づく。「物語」にしばらく手を出さないうちに、本当に抜け落ちている。評判になる作家や作品は、新聞の書評欄や書店でもきっと目にしているはずなのに…。
『家守奇譚』は、それほど厚い本ではなかったので「これなら1日で読めそうだな」と読み始めたのですが、最初の「サルスベリ」の章をひらいてすぐに計画変更。「この本は、ゆっくりと、できるだけ時間をかけて楽しまなくちゃ」と思い直して、居住まいも修正。ソファのクッションの位置を直し、膝掛けを用意して、そのまま数時間は本を開いていることができる体勢に。
途中からは、手元にiPadを置いて「
家守奇譚の植物アルバム」というサイトを見ながら各章の植物を写真で確かめたり、「
児童文学の境界へ 梨木香歩の世界」や「
隠し部屋2号室 梨木香歩の世界」 などにも寄り道しながら、ぐんぐんとペースを落としていく(笑)。
本当に久しぶりに物語の世界に浸かりながら、いい時間を過ごすことができた。
読み終わってから、久しぶりに碁が打ちたくなった。手ほどきしてくれる和尚が、どこかにいないものか。
先週、京都と滋賀に出かけた際、2年ぶりにデザイナーのKさんと会った。
Kさんは、わたしが創業した出版社フィールドノート社で初めて採用したデザイナー。
入社は、たしか設立2年目。数年間一緒に仕事をしてからドイツのデュッセルドルフに移り
日本人向け情報誌のデザインの仕事を経て、5年前から京都で活躍している。
久しぶりに食事でもということになり、Kさんが案内してくれた
京都・祇園の「
田むら」というカジュアルなフレンチのお店へ。
「昨年から○○家(某茶道流派)の雑誌のデザインを、
編集者のご指名で担当することになったんですよ」
と、Kさんはうれしそうに報告してくれた。
5年前、京都に引っ越した時にお世話になった不動産屋の奥さんの紹介で
Kさんはお茶を習い始めた。以来月3回の日曜日は、
かかさずお茶に通っているのだという。
そして今回めぐりめぐって担当することになった仕事が、その流派の雑誌。
好きで、興味をもって続けていると、そんなこともあるのですね。
もちろん偶然による要素が大きいのでしょうが、
Kさんの仕事をどこかでみていた編集者が、その仕事を評価して、
自分の担当する雑誌のデザインをKさんに任せてみようと、決めたわけで。
「好き」なら必ずいいことがある…というものではありませんが。
でも、趣味でも、仕事でも、「好き」の熱意は、
アウトプットに影響を与え、相手に伝わるもの。
そういえば、わたしが東京で編集修行をしていた時に
一緒に机を並べて仕事をしていたデザイナー
Rolling阪本氏は、
フォークシンガーの
加川良さんが、俺の歌の原点だとよく話していた。
そして、いまでは彼も加川良さんの仕事をしている。
当時も
いまも歌い続けるシンガー・ソング・デザイナー・Rolling阪本氏。
今年の1月からはじめている
『コトラーのマーケティング3.0』読書会の2回目。
メンバーは、Oさん、Nさん、そして弊社の若手K君とわたしの4名。
今日の課題は、第2部 戦略。
「消費者に対するミッションのマーケティング」
「社員に対する価値のマーケティング」
「チャネル・パートナーに対する価値のマーケティング」
「株主に対するビジョンのマーケティング」の各章。
第2部は、優れたミッションを策定したうえで、
企業をとりまく各インフルエンサーに対する、
ミッションと行動の一貫性の重要性について説明している。
事前にひととおり読み、 ノートに整理して読書会に望んだのですが、
最後の振り返りの際に、ファシリテイト役のOさんから
ピシャリといただいたお言葉。
「みなさん、もっと読み込んできてください。
テキストは、単なる思考の入り口。
テキストを通じて、私たちを取り巻く社会状況を
どのように読み解くか、が大事だと思います。
それに、読み込むほどに、おもしろくなりますよ」
イタッ。自分はひととおり理解したつもりで発言していましたが、
Oさんにしてみれば手応えのあるジャブが繰り出せていなかったんだな。
前職でたくさんの企業経営者と仕事をしてきたNさんの説得力ある発言に比べても、
自分の発言がいかにテキストの文字を追いかけただけの、浅いものだったか…
…はずかしいなぁ。K君も汗かいていたな(笑)。
この場に限らず、きっとほかの場面でも
相手の期待レベルまで達していない発言を
あちこちで繰り返していそうだな…反省。
もちろん、深読みするのは、時と場合を選ぶことも
読まなくては…ですね。

今日は、お知らせです。
来月の4月23日(土)、24日(日)の二日間、清水駅前銀座を会場に、
eしずおかブロガーさんのお店が、
リアルに出店できるイベント
「eしずおかフェア with 清水駅前銀座」
http://news.eshizuoka.jp/e706554.html
を開催することになりました。
ご協力いただくことになりました清水駅前銀座商店街さん、
ありがとうございます。
「eしずおかブログ」もおかげさまで4周年。
現在の約12000名の会員さんと
約7000個のブロガーさんと一緒に楽しむ
感謝祭にしたいと考えています。
もしかして、わたしが一番楽しみにしているかも。。。
イベントを通じて、eしずおかブロガーさん同士の
リアルなつながりを深めるきっかけになればうれしいな…と。
イベントの主役にあたる
eしずおかブロガーさんによる
ブースの募集が始まりました、
↓ ↓ ↓
http://news.eshizuoka.jp/e706554.html
作品を展示したり、商品を販売したり、占いやマッサージを行ったり…
そう、eしずおかブログのユーザーであれば、
あなたもブース出店ができます!
詳しくは、
こちらをご覧ください。