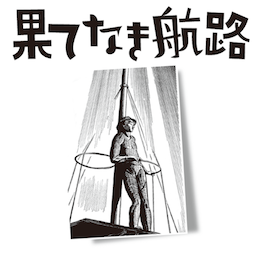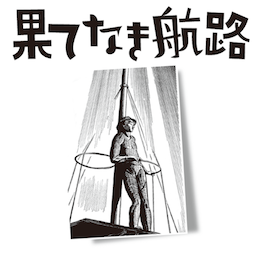
昨日は、「東京国際ブックフェア/国際電子出版EXPO2011」に出かけてきた。例年と違っていたのは、出席した専門セミナーが「東京国際ブックフェア専門セミナー」でも、「eBook専門セミナー」でもなかったこと。今回参加した専門セミナーは、東京大学の重田助教による「講義のオープン化は、何をもたらすのか?」と、関東学院大学辻森教授の「効果が上がるリメディアル教育!〜ソーシャルネットワークを利用した事例」の2本。いずれも「教育ITソリューション専門セミナー」だ。
eBookリーダーや電子書籍の作り方、売り方などは、コンテンツの中身ではなく情報を載せる器の話。ビジネスとして、しっかりと押さえておくとして、いまは、現実にすでに起きていること、始まりつつあることに興味が惹かれる。
「講義のオープン化」では、「東京大学 iTunesU」と「
東大TV」の2つのプラットフォームを使って、学内の知を社会に公開しはじめている東京大学の事例を紹介。当面は「オープン化」による理念と実利のバランスが課題だとしても、オープンエデュケーションの潮流は世界的な動きであって、結果的に大学の価値を高めることにつながるという筋書きである。身近でリアルな事例としては、静岡大学理学部が取り組んでいる「
静岡大学サイエンスカフェ」も講義のオープン化の先進的な事例だと思う。もうひとつの「効果が上がるリメディアル教育!」で紹介された、ソーシャルネットワークを利用した入学前の学生の学力向上や孤独感からの解放の取り組みも興味深いものでした。
「東京国際ブックフェア/国際電子出版EXPO」会場で唯一話を聞いたのは、Robert Stein 氏(本の未来研究所代表)と 萩野 正昭(
ボイジャー代表取締役)による トークイベント「果てなき航路 ー日米デジタル奮戦記」。
ボイジャーは、国内の電子出版界では草分け的存在の会社。これまでニッチで異端児的な見られ方をされていたのではないかと思いますが、今年のブースは例年より広く、大勢のスタッフが参加していた。昨年の「電子書籍元年」を経て、ようやくメインストリームに躍り出た…そんな勢いを感じました。92年の創業以来の電子出版の道のりは、まさに「果てなき航路」だったことは想像に難くないが、現在の状況も楽観視せず、いま尚「果てなき航路」のまっただ中を航海している、そんな強い意志が萩野社長の言葉から伝わってきました。
■パンフレット「果てなき航路 」のPDFファイルは、ここからダウンロードできます。
http://voyager.littlestar.jp/dl/tibf2011/main_panph_tibf2011.pdf
(「果てなき航路 」より一部抜粋)
「どこかで必ずあなたの本を待つ人がいる、そう信じることから電子出版は生まれました。あなたの本は決しておおくの人々には読まれない、そう嘆くことから電子出版はつくられました。紙と印刷という人類の偉大な発明がありながら、冷たい機械をとおして読む辛い方法を選ばねばならなかったのは、売れないとわかっても声を発することを諦めたくなかったからです。人間として私たちが世に送りだすすべてが祝福されるものばかりではない、しかしその中に忘れさることのできないものが消えずに残されています。どんな方法を使ってもこれらを届けることは私達の仕事の一つです。テクノロジーを頼った理由がここにあります。
これはボイジャーが約20年前の創業時、電子出版のためのツールとして発売した「日本語版エキスパンドブック・ツールキット」のパンフレットに書かれた言葉を受け継いだものです。「電子書籍元年」と喧伝された2010年ですが、いま振り返るとその成果は乏しく、まだまだ電子書籍は私たちにとって身近なツールにはなっていません。
…自分たちが何を求めてデジタルの世界に入ってきたのか、忘れない自分たちの失望、そして忘れない自分たちの希望、これらを常に思い起こす必要があるとおもいます。想いつづけてきたデジタルという新しい出版――そこにいったい何が生じた「電子書籍元年」だったのでしょうか。多少電子書籍は売れたのかもしれません。しかし読者がそれを買ったというだけのことで、自分たちがそこで何かをしうる余地など拓けたようには見えません。ただ買うことを求められる仕組みが発展しただけです。
一方で買う以前に、会員登録さえままならない仕組みが依然として色濃く残っています。ご大層なシステムはハッキングされたりダウンしてばかりです。著作権保護(DRM=Digital Rights Management)の強化は、相変わらず買っても読めない人の数を膨大なものにしています。強化すればする程、買った本は一定の書店の仕組みに強く規定されていきます。自分の買った本なのに常に鎖や綱が付いているのと同じです。違うのはその鎖や綱が私たちの目に見えないだけです。」
帰りの新幹線は満席で、通路に立ったまま静岡へ。品川駅から偶然にも、
finoに参加している大手IT企業F社のAさんが乗って来た。お会いするのは何年ぶりだろう。会場で聞いてきたばかりの関東学院大学の「効果が上がるリメディアル教育!」の話をしたら、「関東学院大学さんに、そのSNS導入のプレゼンをしたのは僕ですよ…」ですって。このつながりは、超SNS現象?