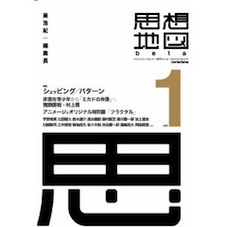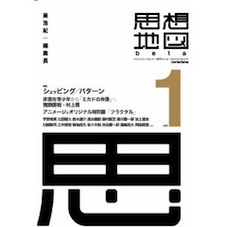
今週の月曜日、この春入社した池戸君、伊藤さんと新卒読書会を行った。テキストは『
思想地図β-1ーショッピング/パターン』の中から、社会学者のチャーリーこと
鈴木謙介氏が担当した「テーマ化される消費都市」の章。
人生の最後にディズニーランドへと旅をする老夫婦(道中での食事はマクドナルド)を描いた米国の小説『ザ・レジャー・シーカー』(マイケル・ザドリアン)を導入にして、人は「過去を通してしか、人生を確かめられない」ものであり、「“老い”は、子孫の世代においては、 “ 消費”という一点で結びついている」という視点で、シニア世代だけでなく、その子ども世代にも受け入れられている「ノスタルジー」の市場化、消費空間におけるテーマ化について取り上げている。
テーマ化とは、対象となる施設やモノを、それとは関係のない 商業的な付加価値化を目的に設計された一連の要素に統一感を与える表現。「テーマ」と「テーマ化」された対象との間には何の関連もなく、何でも「テーマ」になるし、オリジナルの存在も問わない。「ノスタルジー」というテーマも、現実と異なっていてかまわないのだ。そして、消費空間におけるテーマ化は、オリジナルとの間の「ズレ」こそが商業的な付加価値を生んでいる…。つまり「商売」になるということ。
横浜ラーメン博物館などのフードテーマパーク、大江戸温泉物語、イオンモールの昭和を模した駄菓子屋1丁目1番地、羽田空港の「江戸小路」、「3丁目の夕日」、古民家をリノベーションしたカフェ…、ホンモノかどうかは問題ではなく、「商売」になるような味付け(テーマ化)ができていればそれでいい。日常生活の中のさまざまな空間で、多様なテーマ化が行われ、わたしたちはさらなる消費を促されているというわけだ。
20代前半の伊藤さんと池戸君の反応は、「ノスタルジー」消費の中でも、駄菓子などは親はよろこんでいるけど、自分たちは「色がスゴイ」「カラダに悪そう」とは思うけど、だから買って食べたいとは思わない、のだそうだ。そりゃそうだよね。まぁ今時「チクロ」は入っていないはずだけど。それに、 古民家をリノベーションしたカフェは魅力に感じるけど、それは「ノスタルジー」からではなく、たんにオシャレに思えるから…だそうです。
テーマ化された消費現場では、テーマに沿った「パフォーマティブ労働」と呼ばれるロールプレイ(労働)が求められる。そこでは、一般的に高度なコミュニケーション能力が求められるにもかかわらず、給与水準も低く、離職率も高い。それでも、働き手は、労働そのものが自己表現の一部であり、「やりたいこと」と生活の糧を得ることのバランスを追求した結果だと受け入れる。。。
某テーマパークと某コーヒーチェーンが大好きで、そこのスタッフの振る舞いに感化されてバイトしている友人を、ちょっと引いて見ている自分がいる、という伊藤さんの話しには、そういう目線をもっていることに安心した。
この日の読書会の最後に、買い物に「うしろめたさ」を感じるという伊藤さんと、給料日前には何に使おうか、ためらうことなく決めているという池戸君の、「消費」に対する考え方の違いがはっきりとわかれて、興味深かった。買い物についてポジティブなイメージをもっているか、それともネガティブか、いつかアンケートなどで客観的なデータを取って比較してみたいテーマだ。
消費に「うしろめたさ」を感じるという伊藤さんは、買い物には、それを肯定してくれる理由が必要で、それがあると安心できるという。3.11の大震災以降、ますますその傾向は強くなると思う、という伊藤さんの意見は、世の中のある一定の層の方に共通する感覚かもしれませんね。その一方で「消費でストレス発散」という層もいるわけで…。
情報を仕事として扱う私たちは、生活者のみなさんにもっと耳を傾ける必要がありそうだとあらためて実感した読書会でした。
給料日前の池戸君がコツコツと買い物リストを作っている姿を想像して、なぜかうれしくなった。
先日参加した「文化系トークラジオ Life in 川口ーまちのかたち、買い物のかたち」のイベントで、「ぼくは、ビビアン・ウエストウッドしか着ません」という立教大学の学生に対して「
君は、本当は40代じゃないの。君のような学生さんがいて安心したよ」とつっこみを入れた柳瀬さんの気持ちと同じかな。